特定技能外国人を採用するには、外国人が「特定技能試験」に合格していることが必須条件です。しかし、試験の種類や申し込み方法、実施スケジュールは16分野ごとに異なり、「どの試験をいつ受ければいいのか分からない」という声も少なくありません。
本記事では、特定技能試験の基本から、日本語試験・技能試験の詳細、分野別の申し込み方法とスケジュール、合格率まで、採用担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
これから特定技能外国人の採用を検討している企業の方、すでに雇用している外国人の2号移行を支援したい方は、ぜひ最後までご覧ください。
在留資格「特定技能」とは?
在留資格「特定技能」は、2019年4月に新たに設けられた在留資格です。人手不足が著しい特定産業分野の16分野で「一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる」ことを目的にしています。
近年、特定技能の在留者数は急増しており、出入国在留管理庁が公表している特定技能外国人の在留者数によると、2025年6月末には約33万人もの特定技能取得者が在留しています。

現在、日本で最も注目度が高い在留資格で、日本政府は2029年までに82万人まで増やすという政策目標を掲げており、今後も在留者数は急速に増加していくことが見込まれます。
なお、特定技能外国人の受け入れについて知りたい!という方は、「特定技能とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説」の記事をご確認ください。
特定技能の対象業種・分野は?
特定技能は全ての産業・業種が対象ではなく、国内産業の中でも特に人材不足が深刻とされる、16の特定産業分野においてのみ受け入れが可能です。
2024年3月末には、従来の12分野に4分野(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)が追加され、現在は16分野となっています。単純労働を含めた就労が外国人に対して初めて認められた在留資格として大きな注目を集めました。
それぞれ管轄省庁が異なるため、受け入れ基準や申請の流れなどが各分野ごとに異なります。詳細は各分野の解説ページをご覧ください。
特定技能1号と2号の違い
在留資格「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」という2つの種類が存在します。
まず「特定技能1号」の在留資格を取得し、一定の条件を満たした外国人は「特定技能2号」へ移行することが可能です。
上記は、特定技能1号と2号の比較表になります。
特定技能1号は即戦力レベルの人材、特定技能2号は熟練技能を持つ人材という位置づけです。
特定技能2号は、当初「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみでしたが、2023年6月に大幅に拡大されました。
現在、介護と新設4分野(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)を除く11分野で特定技能2号の受け入れが可能です。 なお、介護分野については、一定の要件を満たすことで在留資格「介護」への変更が可能です。在留資格「介護」は特定技能2号と同様、在留期間の制限がなく、家族の帯同も認められています。
特定技能1号と2号の違いについては「特定技能2号とは?1号・2号の違いや取得要件、試験について徹底解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。
特定技能を取得する2つのルート
特定技能1号を取得するには、以下の2つのルートがあります。
【ルート①】特定技能試験に合格する
各分野ごとに定められている「技能評価試験」と「日本語試験」に合格し、在留資格を取得するルートです。 また、介護分野においては、上記2つに加えて「介護日本語評価試験」の合格も必要になります。
【ルート②】技能実習2号を良好に修了する
技能実習2号(在留期間:3年)を良好に修了、もしくは技能実習3号(在留期間:5年)の実習計画を満了した後に、特定技能1号へ在留資格変更をするルートです。このルートを活用する場合、先の技能評価試験の合格は不要となります。
ただし、技能実習時と同じ産業分野において特定技能1号へ資格変更する場合に限られる点は注意しましょう。技能実習時と別の分野へ転職する場合は、転職先企業の産業分野における特定技能評価試験の合格が必須となります。
本記事では、ルート①の「特定技能試験に合格する」方法について、試験の種類から申し込み手順、実施日程、合格率まで詳しく解説していきます。

特定技能試験の基本|必要な試験と受験要件
ここからは、特定技能1号試験について、より詳しくみていきましょう。
特定技能1号に必要な2つの試験
特定技能1号の在留資格を取得するには、「技能試験」と「日本語試験」の2つの試験に合格する必要があります。
技能試験は、各分野で即戦力として働くために必要な知識や技能を評価する試験で、16分野それぞれで異なる試験が実施されています。一方、日本語試験は、日常生活や職場でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測る試験です。
この2つの試験に合格することで、「特定産業分野において相当程度の知識または経験を必要とする技能」と「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力」を有していることが証明されます。
ただし、介護分野においては、上記2つに加えて「介護日本語評価試験」の合格も必須となります。また、繰り返しになりますが、技能実習2号を良好に修了した外国人は、同一分野への移行に限り、これらの試験が免除されます。
①技能試験(分野別評価試験)
技能試験は、各分野で定められた業務を遂行するために必要な技能水準を評価する試験です。16分野それぞれで試験内容、実施機関、受験方法が異なります。
例えば、介護分野では「介護技能評価試験」、外食業分野では「外食業特定技能1号技能測定試験」といったように、分野ごとに専門的な知識や技能が問われます。試験形式は学科試験のみの分野もあれば、実技試験を含む分野もあり、CBT(コンピュータ・ベースド・テスティング)方式で実施される試験が多くなっています。
②日本語試験(JLPT・JFT-Basic)
日本語試験は、「日本語能力試験(JLPT)」または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」のいずれかに合格する必要があります。
JLPTはN4以上(基本的な日本語を理解できるレベル)の合格が求められ、年2回(7月・12月)実施されます。一方、JFT-Basicは250点満点中200点以上の取得が必要で、年6回実施されるため受験機会が多いのが特徴です。
どちらの試験も、日常会話や基本的な読み書きができる日本語能力を証明するもので、いずれか一方に合格すれば要件を満たします。
特定技能2号に必要な試験
特定技能2号を取得するには、1号と同様に各分野で定められた「特定技能2号評価試験」に合格する必要があります。
2号試験は1号試験よりも高度な技能水準が求められ、出題内容の難易度も上昇します。加えて、業種によっては、複数の作業員を指導しながら業務を遂行し、工程を管理できる熟練レベルの技能を証明(2年以上の職長経験・管理経験など)する必要があります。
さらに、外食業など一部の分野では、日本語能力試験N3以上に合格することも求められています。出題内容は全て漢字前提(一部の試験ではふりがながつくこともある)での出題となるため、どの分野においても一定の日本語能力は求められると言えるでしょう。
現在、介護と新設4分野(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)を除く11分野で2号試験が実施されています。
なお、介護に関しては、介護福祉士国家試験に合格することで、在留資格「介護」へ切り替えることが可能になります。
特定技能試験は16分野ごとに個別に実施されている
特定技能の技能試験は、16の全分野で統一された試験ではなく、各分野ごとに個別に実施されています。
各分野の試験を管轄する省庁と運営機関が異なるため、試験の実施頻度、スケジュール、申し込み方法、受験料などもすべて分野ごとに異なります。
そのため、受験を希望する分野の最新情報を、各分野の管轄省庁および試験運営機関のWebサイトで確認する必要があります。
国内試験と海外試験の実施状況
技能試験は日本国内だけでなく、二国間協定(政府間の協力覚書)を締結している国々でも実施されています。これにより、海外在住の外国人が現地で試験に合格してから来日することも可能です。
現在、二国間協定を締結している国は以下の通りです。

ただし、以下の点に注意が必要です。
- 二国間協定締結国でも、試験を実施していない国がある
- 国によっては実施されていない分野がある
- 実施されていても開催頻度が極端に少ない場合がある
海外で試験が実施されていない国の方は、短期滞在ビザで来日して日本国内で受験することも可能です。
二国間協定についてもっと詳しく知りたいという方は以下の記事も併せてご覧ください。
▶【特定技能制度の二国間協定とは】特定技能送り出し国ごとの手続きをご紹介
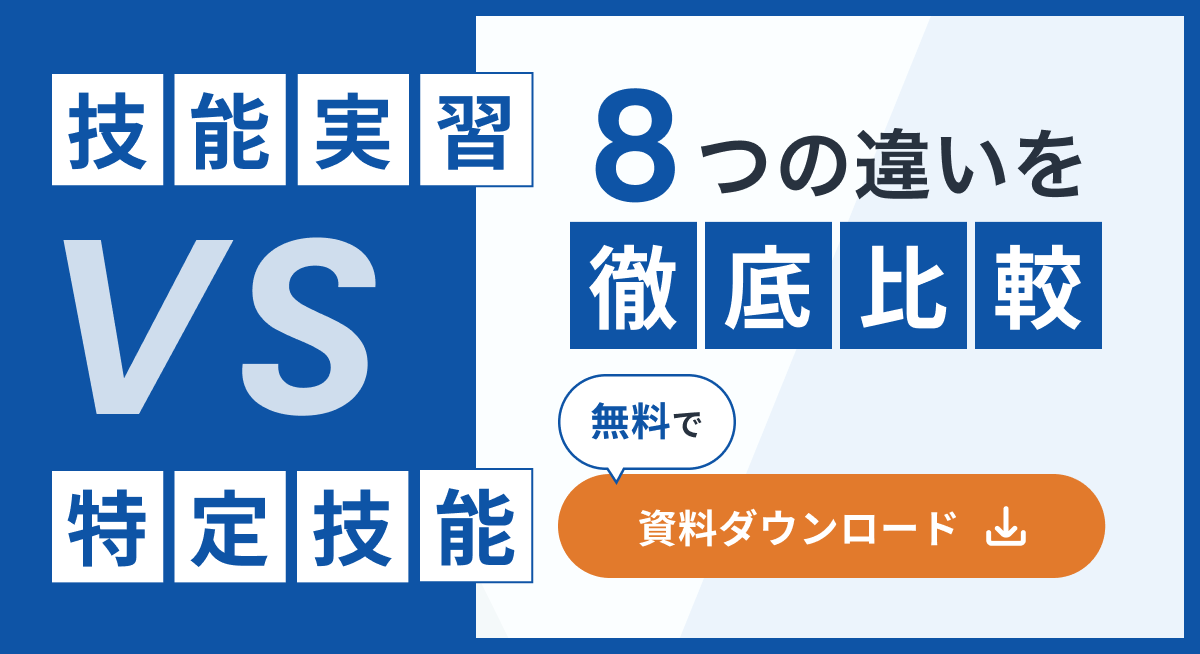
技能試験の申し込み方法・スケジュール・過去問題
以下に、既存16分野における簡単な技能試験の概要、各試験管轄機関のURLを添付しておりますので、ご確認ください。
介護分野
実際はコンピュータ上で回答するCBT方式で実施になります。国内外問わず、試験の実施頻度が高く、日本としても力を入れていることが伺えます。特に国内試験に関しては、毎月1,000名近くの受験者がおり、合格率も約65%〜72%程度で推移しています。ただ、国外試験の合格率に関しては、国や月によって約40%〜90%とばらつきがあります。注意点として、介護分野のみ、特定技能評価試験に加えて「介護日本語評価試験」にも合格しなければなりません。
・試験運営機関:厚生労働省
・試験科目:介護技能評価試験(学科40問・実技5問)、介護日本語評価試験(15問)
・試験日程:こちら(国内)からご覧ください
・申し込み:国内外ともに申込みはこちらから
・介護分野の試験サンプル
ビルクリーニング分野
イラスト等を見ながら行う判断試験に加えて、実際に作業を行う試験が課されます。一定の条件を満たしている場合(受験申請者が20名以上など)、出張型試験も実施しています。過去の合格率は国内試験で概ね70%となっています。
・試験運営機関:公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
・試験科目:学科試験(20問)+実技試験(30問)
・試験日程:国内 / 国外
・申し込み:国内外ともに申込みはこちらから
・ビルクリーニング分野の過去問題
工業製品製造業
製造業の中でも、機械金属加工、印刷・製本区分など10区分に細分化され、それぞれCBT方式の学科試験がメインに実施されています。合格率は区分や実施回によってバラツキはありますが0〜40%程度とかなり低い水準となっていますので、合格するには一定のハードルがある点にご注意ください。
・試験運営機関:経済産業省
・試験科目:学科試験(30問)+実技試験(10問)
・試験日程:こちらをご覧ください
・申し込み:こちらのページからマイページ登録することで申し込みできます
・製造3分野のサンプル問題
建設分野
建設業は土木・建築・ライフライン設備の3つの試験区分に細分化され、それぞれCBT方式の学科試験と実技試験が課されています。以前は試験の実施回数等かなり少なかったのですが、現在は国内外でほぼ毎月試験が実施されるようになっています。国内試験の合格率は40%〜60%程度で、区分によって大きく変動してきます。詳しくは一般社団法人建設技能人材機構HPの試験結果をご覧ください。
・試験運営機関:一般社団法人建設技能人材機構
・試験科目:学科試験(30問)+実技試験(20問)
・試験日程:こちらをご覧ください
・申し込み:こちらのページからマイページ登録し、申し込みできます
・建設分野のサンプル問題
造船・舶用工業分野
溶接・塗装・鉄工・仕上げ・機械加工・電気機器組み立ての6区分に細分化されます。国内試験の場合、集合形式と出張形式の2つの実施パターンがあり、出張形式での試験合格率はかなり高く、ほぼ100%となっています。国外試験は2024年6月現在で予定されているものはありません。
・試験運営機関:一般財団法人日本海事協会
・試験科目:学科試験(30問)+実技試験
・試験日程:こちらをご覧ください
・申し込み:こちらの問い合わせ先へ受験申請の連絡をし、必要書類を提出する必要があります
・造船・舶用工業分野のサンプル問題
自動車整備
学科試験とイラスト等を用いた状況判断等試験を行います。国外試験はフィリピン、ベトナム、インドネシアで実施されており、ほぼ毎月試験が実施されています。受験者数が公表されていないため、合格率は算出できなくなっています。
・試験運営機関:一般社団法人日本自動車整備振興会連合会
・試験科目:学科試験(30問)+実技試験(3課題)
・試験日程:国内 / 国外
・申し込み:こちらから申し込みが可能です
・学科試験のサンプル
航空分野
2つの区分のうち、空港グランドハンドリングは国内では年に4回、東京と大阪で試験が実施され、海外では2025年度はフィリピン、ネパール、インドネシア、スリランカで実施されています。一方、航空機整備区分は2025年度で国内では1回、モンゴルとフィリピンでの実施のみです。
・試験運営機関:公益社団法人日本航空技術協会
・試験科目:学科試験+実技試験
・試験日程:こちらをご覧ください
・申し込み:こちらをご覧ください
・グランドハンドリングのサンプル
・航空機整備のサンプル
宿泊分野
CBT方式で学科試験と実技試験が実施されます。国内では毎月実施されており、国外ではインド、インドネシア、ネパール、フィリピン、スリランカ、ミャンマー、ベトナムで同等頻度で開催されています。国内試験の合格率は50%前後となっており、多少ハードルが高くなっています。
・試験運営機関:一般社団法人宿泊業技能試験センター
・試験科目:学科試験(30問)+実技試験(6問)
・試験日程:こちらをご覧ください
・申し込み:こちらからマイページ登録することで申し込み可能です
・学科試験のサンプル
農業分野
畜産農業と耕種農業の2つの区分に細分化されます。学科試験と実技試験が実施されますが、双方ともに正誤式及び択一式試験になります。国内外でほぼ毎月試験が実施されており、合格率も80%〜90%とかなり高い水準となっています。
・試験運営機関:一般社団法人全国農業会議所
・試験科目:学科試験+実技試験(学科、実技合わせて70問程度)
・試験日程:国内 / 国外
・申し込み:こちらから申し込み可能です
・試験のサンプル
漁業分野
漁業と養殖業の2つの区分に細分化されます。学科試験と実技試験が実施されますが、双方ともにCBT方式で実施されます。国外ではインドネシアとフィリピンは養殖業区分のみ実施されており、国内試験とあわせて比較的高い頻度で開催されています。合格率はばらつきがあるのですが、約40〜50%程度です。
・試験運営機関:一般社団法人大日本水産会
・試験科目:学科試験+実技試験
・試験日程:国内 / 国外(インドネシア)
・申し込み:国内(漁業)、国内(養殖業)・フィリピン 、 インドネシア
・試験問題のサンプル
飲食料品製造業分野
マークシートを活用したペーパーテスト方式になります。HACCP等の一般的な衛生管理に関する内容が出題されます。国外ではフィリピン、インドネシア、ベトナム、ミャンマーで実施されており、合格率は約60%程度となっています。国内試験においても合格率は75%程度と高い水準となっています。
・試験運営機関:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
・試験科目:学科試験+判断試験
・試験日程:国内 / 国外
・申し込み:国内 / 国外
・学習用テキスト
外食分野
マークシートを活用したペーパーテスト方式になります。飲食料品製造業と同じく、HACCP等の一般的な衛生管理に関する内容が出題されます。海外でも開催されており、合格率は67%程度となっています。国内試験においても、合格率は60%程度で徐々に合格率が上がってきています。
・試験運営機関:一般社団法人外国人食品産業技能評価機構
・試験科目:学科試験(30問)+実技試験(15問)
・試験日程:国内 / 国外
・申し込み:国内(マイページ登録) / 国外
・学習用テキスト

特定技能試験の難易度と合格率
特定技能試験の合格率はどの程度かをいくつかの分野で見てみましょう。
以下の表が各分野のおおよその技能試験合格率です。
合格率は開催回や国内外、区分によって異なりますが、総じて特定技能1号の方が合格率は高く、2号の方が合格率としては低い傾向があります。
ただし、多くの分野で年に複数回試験が実施されているため、一度不合格になっても再チャレンジは可能です。
介護分野については、他分野とは異なる注意点があります。 在留資格「介護」へ移行する際には、特定技能2号試験ではなく「介護福祉士国家試験」に合格する必要があります。
この試験には以下の厳しい条件があります。
- 受験資格:介護施設での実務経験3年以上+実務者研修修了
- 実施頻度:年1回のみ
- 合格率:30%台前半
つまり、初めて特定技能1号で来日した外国人の場合、5年間の在留期間中に受験チャンスは実質2回しかありません。加えて合格率も低いため、介護分野は他業種と比較してとりわけハードルが高い点に注意が必要です。
特定技能2号試験不合格でも1年間延長できる?
2025年の法改正により、特定技能2号評価試験で不合格となった1号特定技能外国人でも、一定の条件を満たせば在留期間を1年間延長できる特例措置が設けられました。
この延長が認められる要件は以下の通りです。
- 合格基準点の8割以上を取得していること
- 申請人の誓約:試験合格に向けた努力、合格後の2号申請、不合格時の速やかな帰国
- 受入機関の体制:継続雇用の意思と、試験合格に向けた指導・研修・支援体制の保有
この制度により、特定技能1号の在留期間(最長5年)を超えても、2号試験の合格を目指しながら最大1年間日本での就労を継続できます。ただし、延長期間中に2号試験に合格できなかった場合は、速やかな帰国が求められる点には注意が必要です。
ただし、全ての分野ではなく、実施開始時期も分野によってばらつきがありますので、こちらの出入国在留管理庁ウェブサイトを併せてご覧ください。
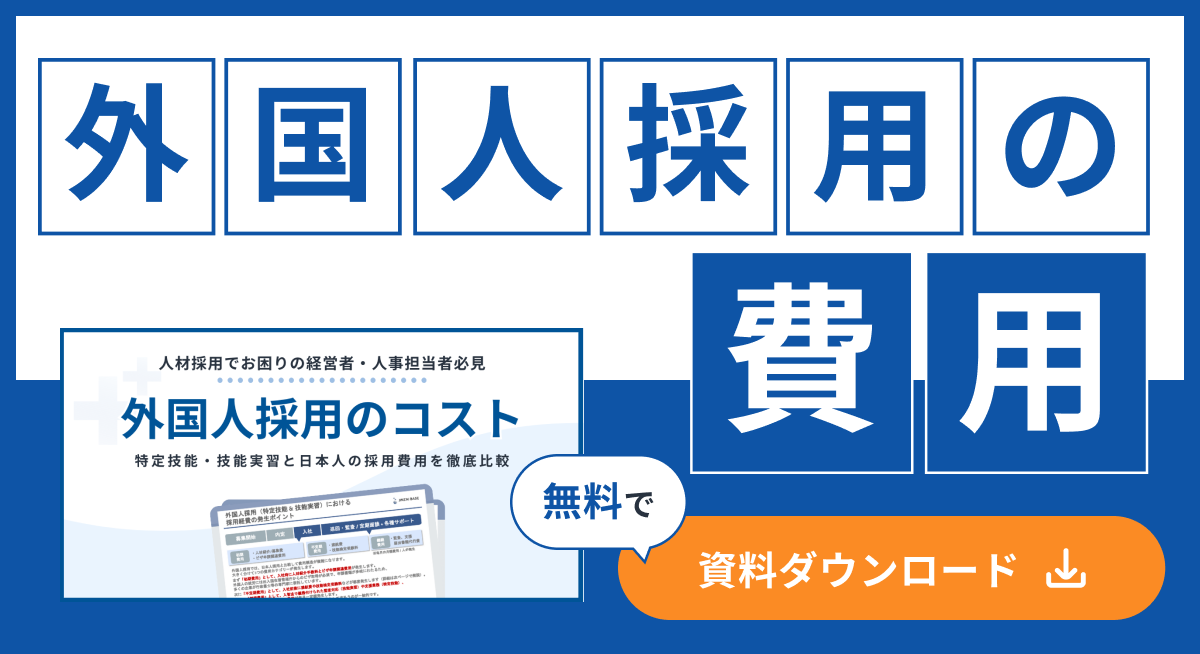
特定技能試験に関する注意事項
ここでは、特定技能試験に関する注意事項を見ていきましょう。
国内試験の実施スケジュールが分野ごとに異なる
先述の通り、特定技能は分野ごとに管轄する省庁、試験実施機関が異なるため、国内試験の実施会場、スケジュール、実施頻度などが異なります。
試験の詳細については、上記で記載の「各産業分野ごとの管轄省庁及び試験運営機関の一覧表」の各試験運営機関のリンクまたは、特定技能総合支援サイトよりご確認下さい。
海外試験の実施状況も分野ごとに異なる
国内試験だけでなく、海外での試験スケジュールも分野ごとに異なるため注意が必要です。
更に海外においては、分野によって試験自体の実施の有無も変わってくるためより一層注意しなくてはなりません。
海外の試験日程についても、特定技能総合支援サイトにて確認ができます。
おわりに
今回は在留資格「特定技能」を取得するために必要な試験について、詳しくお話してきましたが、いかがでしたか。
各分野における試験詳細については、本文中でもご紹介している各団体のページも参照して、リサーチしてみてください。
もし、より詳細を知りたい、特定技能外国人の受け入れや委託先を変更したいという場合には、ぜひこちらのサービスサイトからご連絡くださいませ。








.jpeg)


.png)





