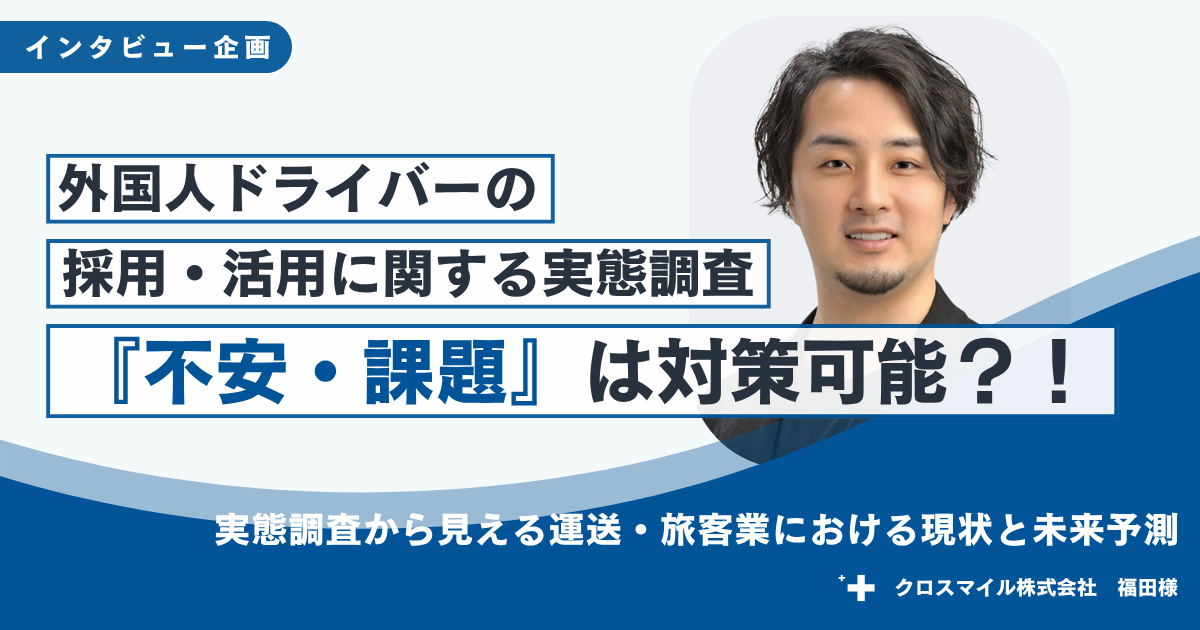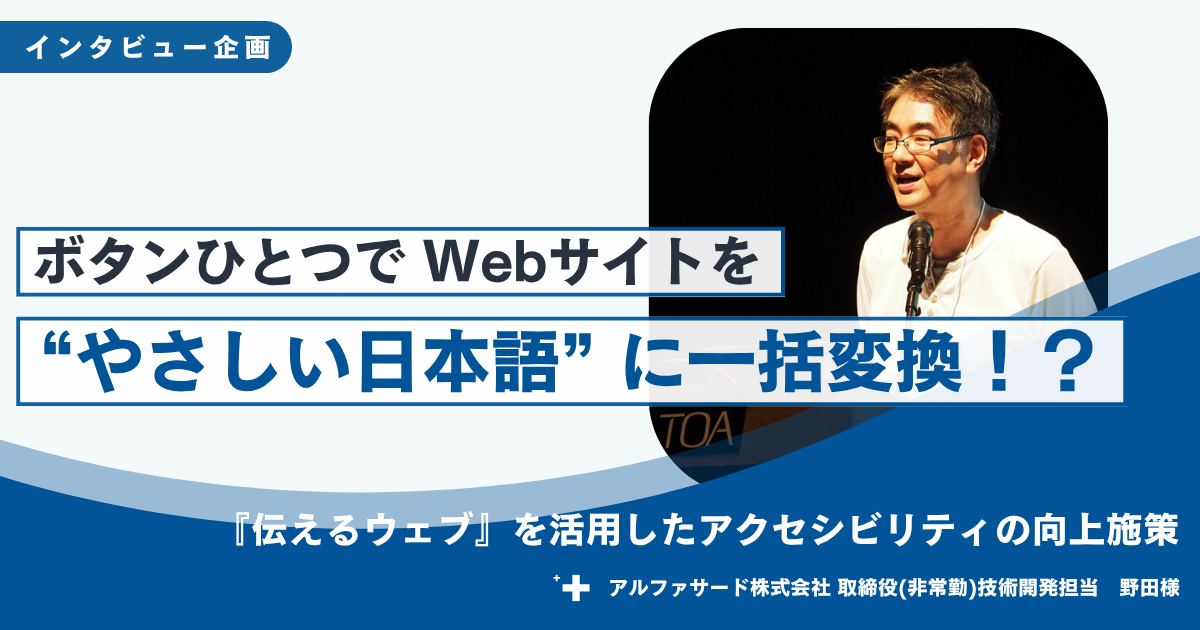介護分野における人材不足が深刻化する中、全国に事業所を展開する株式会社土屋では外国人材の活用に踏み切っています。2020年に設立され、わずか5年足らずで従業員数2,600名を超える規模に急成長した同社では、技能実習と特定技能の両制度を活用した外国人材の受け入れを進めています。
日本全国に事業所を展開し、特に重度訪問介護を主力としながら多角的に福祉事業を展開する株式会社土屋の取り組みは、今後の介護業界における外国人材活用のモデルケースとなるかもしれません。今回は同社 国際企画室 室長の鈴木様に、外国人材の受け入れ状況や今後の展望、そして実際に受け入れを始めてからの現場の反応や課題についてお話を伺いました。
多角的に福祉事業を展開する「介護のトータルケアカンパニー」

ーーー貴社の事業・鈴木様について簡単にお伺いできますでしょうか?
鈴木氏:
私は工場などの生産管理や品質管理、営業など様々な仕事を経験してきましたが、2018年に介護の仕事を初めて経験することになります。
当初は京都・関西の重度訪問介護の現場に入りながら、徐々にコーディネートや管理業務などにステップアップしていきました。その後、中国・四国エリアや九州方面への事業拡大に携わり、各地域の事業所立ち上げや広域マネジメントを担当してきました。現在は、人材不足の課題解消のための外国人材活用に関わっています。
当社のメイン事業は重度訪問介護で、北は北海道から南は九州・沖縄まで、全国各都道府県に最低1事業所を置いて展開しています。これは障害福祉サービスの地域生活支援事業の一つです。それ以外にも、高齢者向けの介護保険サービスとして訪問看護やデイサービス、定期巡回・随時対応サービス、グループホームなどの施設系サービスも提供しています。
また、「カレッジ」と呼ばれる研修事業も行っており、介護職員初任者研修や実務者研修、介護福祉士国家試験対策講座などを提供しています。この研修事業は、介護人材の育成と確保に重要な役割を果たしており、無資格・未経験の方でも介護の仕事に携われるようサポートしています。
さらに出版事業やシンクタンク事業として、福祉現場の研究活動や政策提言も行っています。福祉現場における課題や改善点を研究し、より良いケアのあり方を模索して政策提言につなげるという、未来志向の取り組みです。
このように、介護サービスの提供から人材育成、研究活動まで幅広く手がけており、「介護のトータルケアカンパニー」として福祉・介護分野を総合的にサポートしています。
当社は2020年に設立され、5年足らずですが、現在の従業員数は常勤・非常勤を含めて2,600名を超えています。常勤だけではなく、特に24時間体制の重度訪問介護では、ダブルワークなど非常勤として関わってくださる方も多くいらっしゃいます。
日本人を採用できているが、それでも人材の「絶対数」が足りない

ーーー現在の外国人材の受け入れ状況についてお伺いできますか?
鈴木氏:
現在、技能実習生として3名のベトナム人が入社しており、グループホームで生活支援として働いています。今年の1月末から実際に稼働を始めたところで、まだ2ヶ月ほどです。外国人材の受け入れは、面接から入国までの手続きに半年程度かかるため、昨年の夏前から面接や手続きを進めてきました。
それに加えて、特定技能の外国人として7名の採用内定が決まっており、内訳はインドネシアの方が5名、ミャンマーの方が2名です。現在、入国手続きを進めている段階で、夏から秋頃には実際に現場で働き始める予定です。
ーーー国籍が複数の国にわたっていますが理由があるのでしょうか?
鈴木氏:
外国人材の受け入れを検討する際にいろいろとリサーチしたところ、よく名前が上がってくるのがベトナム、インドネシア、ミャンマー、フィリピン、ネパールなどでした。特にベトナムとインドネシアは他の事業者でも受け入れが多く、介護分野で活躍されている方が多いと聞いています。それぞれの国の国民性なども影響しているのかもしれません。
また、1カ国だけに偏るとリスクもあるため、複数の国から受け入れるようにしています。将来的に人数が増えていくことも想定されますので、様々な国籍の方々が混合して働ける環境を整えることが大切だと考えています。現在は3カ国ですが、今後状況によっては増えるかもしれませんし、逆に特定の国からの受け入れが難しくなる可能性もあるため、リスク分散の意味もあります。
ーーー外国人材の採用に踏み切った背景は何かあったんでしょうか?
鈴木氏:
一般的に言われているように、介護を必要とする方はどんどん増えていく一方で、働く人が減っているという現実があります。つまり、絶対数がどうしても足りないという状況です。日本人だけでは充足できないという根本的な問題があります。
当社も採用サイトを充実させるなど、日本人採用に力を入れています。もちろん、日本人の応募もたくさんありますが、それでも絶対数が足りないという現状です。また、介護は昔から「3K(きつい、汚い、危険)」と言われる職種で、イメージ的に選ばれにくい面もあるかもしれません。「介護はきついでしょう、大変なんでしょう」というような先入観から、職業選択の際に敬遠されがちな面もあります。
そういった背景から、今後さらに人材不足が進むことも見据えて、外国人材の活用に踏み切りました。当社が全国に事業所を展開し、今後もさらに成長していくためには、日本人材だけでなく外国人材も含めた人材確保が不可欠だと判断しています。
技能実習・特定技能の両制度をまずは同時に経験してみる
_%EF%BC%881%EF%BC%89.jpg)
ーーー技能実習と特定技能の両方で進められていますがどんな意図がありますか?
鈴木氏:
技能実習制度の方が歴史が古く、その後に特定技能制度が始まったという経緯があります。最初は技能実習からスタートし、その後に特定技能も取り入れるという形で、両方の制度を経験して良い点・悪い点を見比べながら、より良い方法を見つけていきたいと考えています。
実際に両方の制度を経験してみないと分からない点もありますので、まずは取り組んでみるという姿勢で進めています。それぞれの制度の特徴やメリット・デメリットを実際に体験しながら、当社にとって最適な外国人材の受け入れ方法を模索しているところです。
ーーー今後の採用戦略としてはどの在留資格を中心に考えていますか?
鈴木氏:
経営層での議論の結果、特定技能制度の方にシフトしていく方針です。今年4月から特定技能での訪問介護が解禁されることもあり、当社の主力事業である訪問介護、特に重度訪問介護に外国人材を活用していく上では、特定技能の方がメリットが大きいと考えています。
技能実習でも訪問介護は解禁されていますが、1年以上の経験がないと配属できないなど、課題が多いのが現状です。特定技能の方が、当社のニーズに合っているという判断です。
加えて、育成就労制度についても注視していますが、当社としては現時点では特定技能制度を主軸に据える方針です。
ただ、育成就労も含め、制度の変更や新設については情報収集を続け、必要に応じて戦略を見直していく予定です。いずれにせよ、外国人材の受け入れ拡大は不可避であり、当社にとって最適な方法を模索し続けています。
ーーー国内ですでに働いている外国人を採用するという選択肢はなかったのでしょうか?
鈴木氏:
国外から新しく来る方の方が、採用・育成しやすい面があると考えています。
すでに日本国内で働いている外国人の方で転職を希望される方もいますが、最初から海外から受け入れる方が、当社にとっても育てやすく、根付いていただける可能性が高いと感じています。新たに日本に来る方は、良くも悪くも何も染まっていない状態で、希望に燃えて一生懸命頑張る姿勢が見られることが多いです。
まだ外国人材の受け入れを始めたばかりなので、基本的な正統的なルートからスタートすることが良いと考えています。今後特定技能の方が増えてくると、転職希望者も増えてくると思うので、そうした方々の採用も検討していくかもしれませんが、初めての取り組みということもあり、まずは基本的なスタートの仕方から始めて学んでいきたいと思っています。
「初めて介護に取り組む人」をどう育てていくかという視点が大切

ーーー外国人材の受け入れに対して現場から不安の声などはありましたか?
鈴木氏:
日本全体としてもまだまだ外国人との関わりが少ない中で、言葉や文化、コミュニケーションに関する不安を示す声はありました。また、人材不足が顕著な現場では「即戦力」を求める傾向がありますので、外国人材が本当に活躍できるのかという不安もありました。
ただ、これは日本人でも外国人でも同じことだと思います。当社の主力事業である介護は、無資格・未経験から始める方も多いので、「外国人だから」ということだけで大きな違いはないということを現場に伝えながら進めています。
外国人であることよりも、介護という仕事に初めて取り組む人をどう育てていくかという視点で考えることが大切だと考えています。
ーーー実際に入社された外国人材の方々の働きぶりはいかがですか?
鈴木氏:
面接時は想定した質問への回答を用意してきているので日本語も上手に感じますが、予想外の質問をすると詰まってしまうこともあります。そういう時は、まだ小学生レベルの日本語能力かなと感じることもありました。
しかし、日本で実際に生活し始めて2、3ヶ月でも大きな変化があり、様々な単語を覚えて理解する力がついてきています。日常的に日本語に触れる環境にいることで、急速に日本語能力が向上している印象です。おそらく普段から一生懸命勉強されているのだと思いますが、日々の業務の中でもしっかりと対応できるようになってきています。
皆さん非常に意欲的で、率先して働いてくれています。物怖じせずに積極的に業務に取り組む姿勢は、他のスタッフにとっても良い刺激になっているようです。
ーーー実際に受け入れてトラブルはありませんでしたか?
鈴木氏:
来日前に日本で使える携帯電話の契約をしてくるという話だったのですが、実際には契約されておらず、来日後に急遽契約する必要がありました。こちらも手続きの流れに不慣れだったため、少し右往左往してしまいました。
また、内定が決まっていた1名の方が健康診断でNGとなり、入国できなくなるということもありました。急遽変更する必要が生じ、対応に追われました。外国人材の受け入れでは、こうした予期せぬ事態も起こり得るということを実感しました。
最初の不安は「意外と大したことない」と感じるケースも
_(4).jpg)
ーーー外国人材の育成についてはどのように取り組まれていますか?
鈴木氏:
現在は特別な外国人向けのカリキュラムは用意しておらず、基本的に日本人と同じ方法で育成を進めています。言葉の壁などで時間がかかることはありますが、業務内容自体は日本人と変わらないため、同じ育成方法で対応しています。
今後、受け入れ人数が増えてくれば、母国語での教材なども準備できればいいのではないかと考えています。日本語でのコミュニケーションを円滑にするための特別な取り組みも検討中です。
ーーー登録支援機関の業務を内製化する予定はありますか?
鈴木氏:
現在は特定技能に関しては登録支援機関に入っていただいていますが、将来的には自社で対応せざるを得なくなるのではないかと考えています。当社は全国展開していますので、北海道から沖縄まで全てをカバーするのは外部機関では難しい面もあります。人数が増え、広域に配置するようになれば、自社での対応が必要になってくるでしょう。
ーーー最後に外国人雇用を検討中の介護施設に向けてメッセージをお願いします
鈴木氏:
外国人材活用のきっかけは「人材不足」から始まることが多いと思いますが、これは日本と人材輩出国の双方における社会課題解決にもつながる取り組みです。お互いの良いところで、より良い共生社会が構築できるのではないかと思います。
最初は不安感があるかもしれませんが、ぜひ一歩を踏み出してみてください。実際に始めてみると「意外と大したことなかった」と感じることも多いのではないでしょうか。言葉や文化の壁を心配する声もあるかもしれませんが、外国人の方々も一生懸命に日本語や日本の文化を学ぼうとしてくれますし、私たちが想像している以上に適応力を持っています。
介護の現場での人材不足は今後も続くことが予想される中、外国人材の活用は避けては通れない道だと考えています。まずは一歩踏み出し、共に成長していく姿勢が大切なのではないでしょうか。当社も始まったばかりの取り組みですが、これからも試行錯誤しながら、より良い受け入れ体制を整えていきたいと考えています。
編集後記
今回は、全国展開する株式会社土屋の鈴木様に、介護現場における外国人材活用についてお話を伺いました。
2020年設立からわずか5年で従業員数2600名を超える同社では、ベトナム、インドネシア、ミャンマーから外国人材を受け入れています。技能実習生3名が働き始め、特定技能では7名の採用が内定しています。
「絶対数が足りない」という介護業界の人材不足が浮き彫りになる中、同社は国内転職者より新規来日者の確保を重視し、主力の訪問介護での活用を前提に、今後は技能実習から特定技能へのシフトを見据えています。
「外国人材の活用は日本と供給国双方の社会課題解決につながる」という視点と、「一歩踏み出せば意外と大したことなかった」という経験は、同様の課題を抱える介護事業者に勇気を与えるでしょう。
株式会社土屋の取り組みが、介護業界における外国人材活用のモデルケースとなるのではないでしょうか。