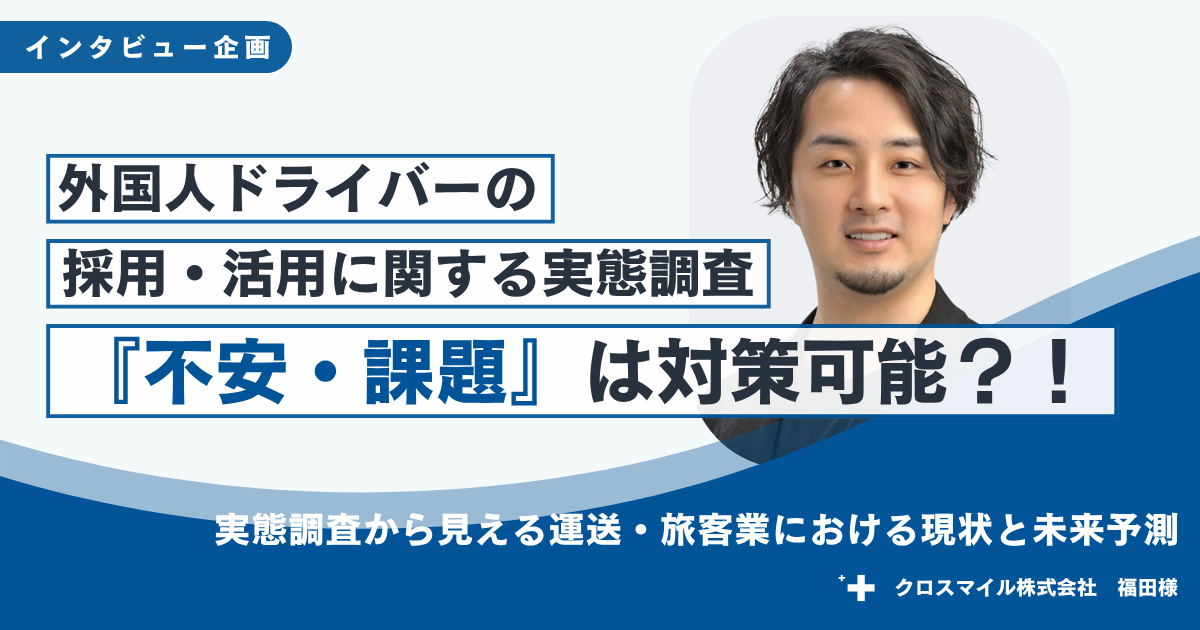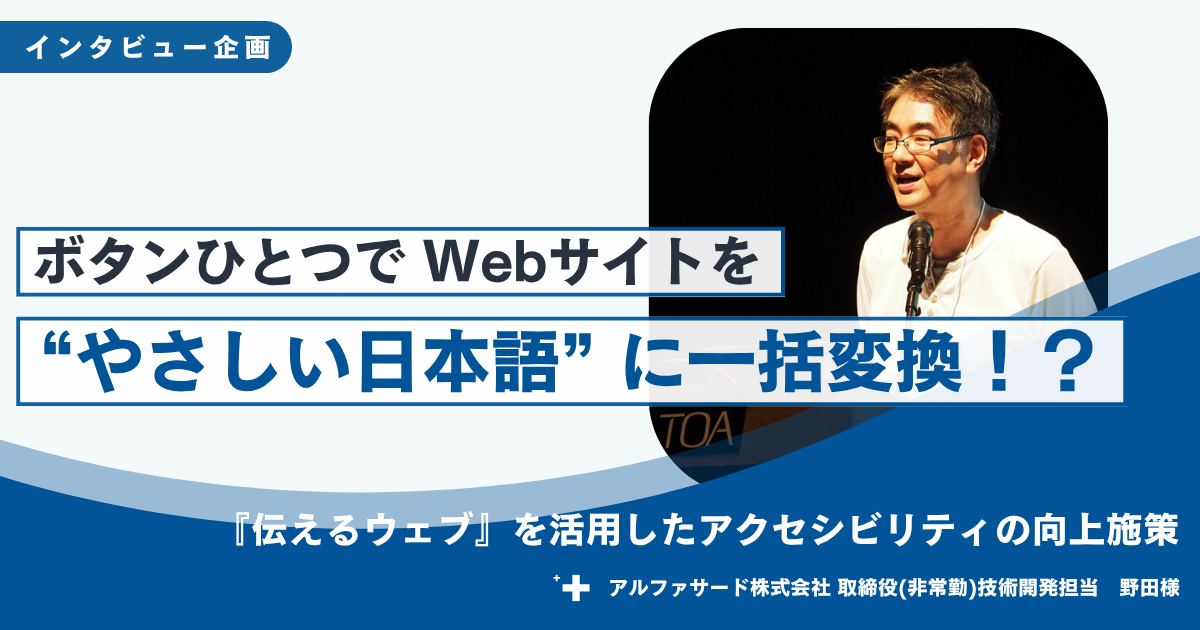世界最先端の子ども向けプログラムを提供する英会話スクール「株式会社アライブ」では、110名の従業員のうち50名近くが外国人という、多様性あふれる組織運営を実現しています。
単なる英会話教室にとどまらず、インターナショナルスクール、STEM教育、子供達向けのリーダーシップ・起業家育成プログラムなど幅広い教育事業を展開する同社。特筆すべきは、外国人従業員の離職率がほぼゼロという点です。
多様な国籍のスタッフが長期にわたって定着し、子どもたちの教育に携わる環境をどのように構築しているのか。今回は代表取締役社長の三井社長に、外国人採用の実態と成功の秘訣について話を伺いました。
「離職を減らし、応募者数を最大化」するための採用戦略

ーーー貴社の事業概要とサービス展開の経緯についてお聞かせください!
三井様:
当社では、英語の保育園であるインターナショナルスクールと、それとは別に午後の英会話教室「アライブイングリッシュスクール」も展開しています。さらに、STEM系の理工系プログラムに特化した「STEMスクール」、昨年度からは学童の「ドリームスクール」も運営しています。
幼稚園や小学校への外国人講師の派遣事業も行っており、名古屋市の椙山女学園高等学校附属小学校のアフタースクールを受託したり、約40の幼稚園・保育園へ外国人講師を派遣しています。また、名古屋市教育委員会やNPOと連携して、小学生、中学生、高校生のキャリア教育も積極的に行っています。
英会話レッスンでは、初心者向けの英会話だけでなく、英語力が高い子供たちには英語で専門分野を学ぶプログラムを提供しています。例えばアート系、SDGs、ハーバード大学のリーダーシップ研究所やシリコンバレーの教育機関・起業家と連携して、子供向けの起業家育成プログラムやリーダーシッププログラムを多数開催した実績があります。
今後はテクノロジー分野にも力を入れていく予定で、もうすぐ新しい教育系マッチングオンラインサービスを4月初旬にローンチする予定です。また、2026年に向けて、新しいコンセプトのカリキュラムを取り入れた教育プログラムの開発を進めています。さらに、事業の幅を一層広げていく計画です。
ーーー法務関係のご経験から教育事業を立ち上げられた理由は?
三井様:
きっかけは私のアメリカ留学経験にさかのぼります。海外の大学に留学中、日本人留学生は日本語を話すことが多く、あまり積極的に発言しないという状況を目の当たりにしました。日本の将来に対しての課題を感じて、「教育」と「英語教育」の必要性を認識しました。
単なる言語としての英語力だけでなく、自分の考えを発信する力、知識を得て考える力を育むことが大切だと考え、2001年に会社を設立しました。
ーーー従業員の構成について教えてください!
三井様:
現在、契約社員及び正社員併せて約50名の従業員がおり、そのうち日本人が25名、外国人が25名程と同じ割合になっています。非常勤の外国人30名及び日本人社員30名を含めると全体で110名ほどになります。
ーーーどのような国籍の方が働いているのでしょうか?
三井様:
アメリカ、イギリス、オーストラリア、スウェーデン、フィリピン、インドネシアなど、本当に世界中の国々から来ています。英語教室である以上英語圏の方も多いですが、国籍にはこだわっていません。
通常、英会話教室では英語圏の講師だけを採用する傾向がありますが、当社ではマーケティングや人事部門などの組織部門にも外国人がいます。特にSTEM教育では、理工系のバックグラウンドや修士・博士号、専門資格を持つ人材が重要になるため、必ずしも英語圏の人材だけではなく、適切な資格や経験を持つ多様な国籍の方々を採用しています。
ーーー採用活動はどのように行っているのですか?
三井様:
求人広告や大学の留学センターへの訪問、外国人向けの求人サイトなど、様々な方法で募集しています。ハローワークでも募集していますし、アメリカやカナダに直接行って面接をすることもあります。
採用媒体によって特徴があり、資格を持つ外国人講師を紹介する求人媒体では費用は高くなる傾向がありますが、資格を持った外国人講師をしっかりスクリーニングした上で紹介してくれるメリットがあります。
ーーー面接はどのように進めていらっしゃるのですか?
三井様:
海外にいる候補者にはオンライン面接を実施し、日本在住の方には可能な限り対面での面接を行っています。
対面の場合は、実際の授業を見学してもらった上で、面接者のレッスンチェックも行います。これは内定前の選考プロセスの一部で、子供たちとの相性や教え方を見るための重要なステップです。面接は全て英語で実施しています。
採用では面接チェックリストを使い、当社の価値観に合う人材を慎重に選んでいます。特に重視しているのは経験やスキルに加え、「子供が好きであること」「前向きで元気で明るいこと」です。チェックポイントごとに点数をつけ、多くの応募者の中から厳選しています。
このように複数のステップを設けているため、選考期間が長くなり、その間に他社で決まってしまうケースもあります。以前に選考プロセスを簡略化したことがありましたが、結果的に採用のミスマッチが生じてしまいました。履歴書と実際の人物像が異なるケースや、「教えること」は好きでも「子供」が好きとは限らないケースもあるため、丁寧な選考が欠かせません。
長い選考プロセスですが、採用できた方々は本当に質の高い人材で、子供たちと笑顔で接し、チームワークも優れています。結果として、日本人スタッフと外国人講師の間にも良好な関係が築かれていますので、このプロセスは間違っていないなと感じています。
ーーー求人媒体やエージェントを活用してもなかなか応募が来ないと悩まれる会社様がいらっしゃいますが
三井様:
その観点ですと、当社は外国人スタッフの応募数や定着率を高めるため、様々な福利厚生にも力を入れています。
そもそもの条件も競合他社と比較した時に、高めに設定しているのは前提として、言語・教育関係の資格取得支援として、資格試験の勉強時間の確保だけでなく、試験費用も会社が負担しています。外国人の方々は自己成長を強く望んでいるので、このような学びの機会を提供することが非常に重要です。
社内イベントも充実させています。リトリートプログラム、社内スポーツ大会、バーベキューなど多彩なイベントを定期的に開催し、日本人と外国人のスタッフが自然に交流できる場を作っています。これらのイベント運営は大変ですが、チームの結束力強化に大きく貢献しています。
また、人事考課システムをオープンにしていることも特徴です。外国人スタッフが自分のキャリアパスを明確に見通せるよう、評価基準や昇進の条件を透明化しています。次のステップに進むために必要なトレーニングやスキルも明示し、成長をサポートしています。
社内会議も含めこうした福利厚生制度の説明では、すべて英語で行われ、公平な待遇により、結果として応募数は堅調に推移しており、加えて離職率も非常に低く、60名近い外国人がいても年間の採用は数名程度で済んでいます。
そのため、そもそも離職が少ないので採用に逼迫することがなく、かつ採用選考する場合には、じっくりと時間をかけて、良い人材を見極められるという好循環が回っています。
外国人採用で大切なのは「偏見・先入観を持たないこと」

ーーー多様な国籍の方を雇用する中で難しさはありましたか?
三井様:
最初は非常に大変でした。宗教や文化、考え方、日々の習慣も全く異なる人たちが集まっていますから。起業当初は分からないことだらけで、様々なトラブルがありました。
しかし、だんだん理解してきたのは、日本に住む外国人は私たち以上に日本のことを勉強しているということです。彼らは日本に来る前から日本について学び、来日後も学び続けています。そのため、日本企業としての価値観を伝えると、思いのほかよく理解してくれるんです。
例えば、「海外は契約社会だから」など、「外国人はこうだから」「この国の人はこうだから」といった先入観を抜きにして、同じように接していくことがとても大切だと気づきました。その結果、10年以上勤続している外国人講師も多く、離職率は非常に低いです。退職は、家族の事情で帰国する場合や結婚で引っ越す場合など特別な理由がほとんどで、通常の退職はほぼありません。また、帰国してもまた出戻ってくる社員も多いです。
ーーー起業当初はどのような課題があったのでしょうか?
三井様:
創業初期には本当に多くの失敗やトラブルがありました。最も大きかったのは文化の違いから生じる勤務態度の問題です。日本人スタッフは有給申請もきちんと行い、時間に正確で、約束の10〜15分前には必ず来るのが当たり前です。一方、外国人スタッフの中には時間の概念が異なり、遅刻が頻繁にあったり、急な欠勤があったりするケースがありました。
また、コミュニケーション面での誤解も多発していました。特に書面での説明が不十分だと「聞いていない」「説明されていない」というトラブルになることがありました。外国人スタッフは契約社会の文化から来ているので、きちんと書面化することが重要なのですが、かといって分厚い契約書を出すと、ルールで拘束されるのでは、という不安にさせるという難しさもありました。
さらに、最初は日本人スタッフと外国人スタッフを区別して扱う傾向があり、それが「日本人の方が優遇されている」「外国人には厳しい」といった不公平感につながっていました。
ーーーどのようにこれらの問題を解決していきましたか?
三井様:
まず、コーチング導入が大きな転機となりました。外国人の上司が部下の外国人に対して「なぜ遅れたのか」「どうしたら定時に来られるか」など、問題解決型のコーチングを行う研修を実施しました。この効果は目に見えて表れ、勤務態度の問題は大幅に改善されました。
それ以外にも、社内の新入社員研修・管理職研修を外部の研修サービスを活用するのに加え、自社でもしっかりとプログラムを構築し、手厚く実施しています。
情報共有の仕組みも整備しました。社内エンゲージメントサーベイを定期的に実施し、共有ツールに関する課題が多く挙げられていたことから、情報共有のルール・仕組みを刷新しました。外国人スタッフからの意見を積極的に取り入れ、改善を重ねたことで、情報の行き違いによるトラブルは激減しました。
何より重要だったのは、「外国人だから」「日本人だから」という区別をやめ、全員を平等に扱う文化を根付かせたことです。最初は難しかったものの、徐々に浸透し、現在では国籍に関係なくお互いを尊重し合う環境が自然と形成されています。
それでも、有給休暇の取得方法には文化的な違いが残っています。外国人スタッフは母国の家族を訪ねるため、一度に2〜3週間の長期休暇を取得することがありますが、これは事業運営上の課題となることもあります。しかし、海外に帰省する必要性を理解し、一人ひとりが生きがいを持って幸せに働けるようなウェルビーイング経営を目指して柔軟に対応しています。
これらの経験から、外国人スタッフとの協働では、偏見を持たず、コミュニケーションを大切にし、相互理解を深めることが何よりも重要だと学びました。
ーーーとても良い組織風土が醸成されていますが特に効果があったことはなんですか?
三井様:
以前から良い雰囲気は醸成されつつあったのですが、強いていうならば、コロナ禍の経験が大きかったと思います。日本語が読めない外国人は、日本のテレビ報道も見られず、CNNなどの海外メディアからの情報だけで非常に不安を抱えていました。
そこで会社として「外国人スタッフは親や家族が海外にいて、日本で一人で暮らしている人も多い。そういう人たちの気持ちを理解することが私たちの理想とする共生社会だ」と発信しました。
そして、総務部が外国人スタッフのサポートを強化し、病院に付き添ったり、資料を英訳したり、定期的に状況を英語で説明しました。また、校舎でもできる限り外国人に社会で起こっている出来事やコロナ時の会社としての対策などを通訳しました。これにより、外国人自らコロナの時期を乗り切ろうと言ってくれるようになり、日本人スタッフと外国人スタッフの絆が深まったと感じましたね。
現在は「誰々が困っているからこうしてあげよう」という助け合いの文化が自然に根付き、心理的安全性が確立されているのではと感じています。
ーーー外国人採用を検討している企業へのアドバイスをお願いします!
三井様:
外国人に長く働いてもらうコツは、偏見を持たないことです。「外国人だから」という先入観を持たずに接することが重要です。日本に住みたい、働きたいと思っている外国人はしっかり日本の文化を学んでいて、馴染もうと努力しています。
また、外国人スタッフは日本語や日本文化を学びたいと思っていることが多いです。高額な福利厚生よりも、日本語を教えてくれる環境や日本についてもっと知る機会を求めていたりします。
コミュニケーションも非常に大切です。日本人は言いにくいことを言わない傾向がありますが、外国人スタッフには理由や目的をはっきり伝え、意見を尊重しながら話し合うと、関係性が大きく変わります。忖度は通じないので、正直なコミュニケーションを心がけることが成功の鍵です。
編集後記
株式会社アライブ 三井社長のインタビューから、外国人採用の成功には「人」として向き合い、互いを尊重し合う文化づくりが重要だということが伝わってきました。特に印象的だったのは、「外国人だから」という区別をせず、平等に接することの大切さです。
コロナ禍という危機的状況での対応が組織の結束を強め、互いに助け合う文化を育んだという点も、危機を成長の機会に変えた好例と言えるでしょう。結果として、離職率の大幅な減少と腰を据えた採用活動という好循環につながっている点は、外国人採用に悩む企業にとって、非常に示唆に富む事例となりそうです。