外国人労働者が退職する際の手続きは、日本人の退職とは異なる点が多く、企業の人事・労務担当者にとって複雑に感じられることも少なくありません。
雇用保険や社会保険の資格喪失手続きに加えて、外国人雇用状況の届出、退職証明書の交付など、外国人特有の手続きが必要です。また、退職する外国人本人にも、出入国在留管理庁への届出や在留資格の手続きなど、期限内に行うべき重要な手続きがあります。
さらに、特定技能外国人の場合は、支援計画の終了報告や登録支援機関との連携など、特別な対応が求められます。
本記事では、外国人労働者の退職時に企業側が行うべき手続きと、外国人本人が行うべき手続きを詳しく解説します。
外国人の退職手続きは日本人と違う?
外国人が退職する際の手続きは、日本人とは異なるのでしょうか?
結論、異なります!
ただ、
- 原則、日本人が退職する場合と同じ手続きが必要
- 追加で、外国人労働者特有の手続きが必要
という認識で問題ありません。
また、外国人労働者本人が実施すべき手続きもあり、この手続きを実施しないと「転職ができない」というケースも発生しかねません。
ここからは、外国人労働者が退職する際に対応すべき事について、全体像を押さえるため、それぞれのカテゴリーに分けて、どのような手続きがあるのか詳しく見ていきましょう。
なお、外国人労働者の転職時の手続き(主に在留資格の申請等)については、「【外国人が転職する際の手続き】ケース別にわかりやすく解説」で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
受け入れ企業が実施するべき退職手続き
まずは、退職する外国人の受け入れ企業側が実施するべき退職手続きについて確認していきましょう。「日本人と同様の手続き」と「外国人特有の手続き」にカテゴリー分けした上で解説していきます。
全体像は以下の表の通りとなっております。
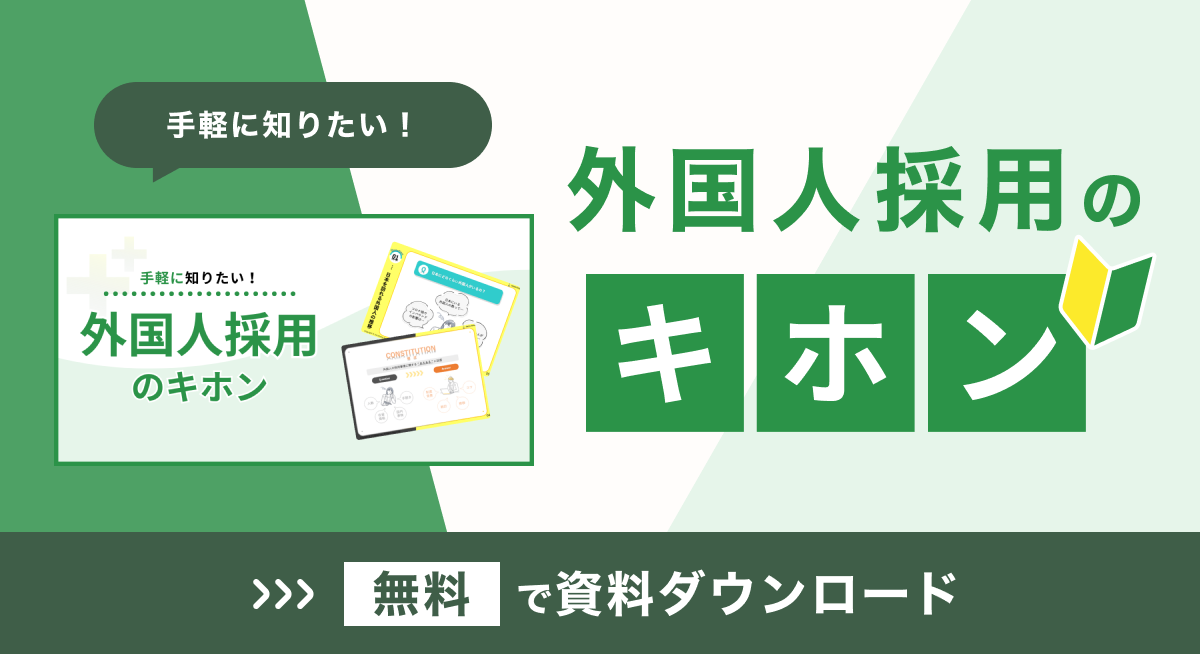
【企業側】外国人労働者の退職時に行う具体的な手続き
まずは企業側が実施する外国人労働者の退職手続きについて見ていきましょう。
雇用保険資格喪失手続きと離職票の交付
外国人労働者が退職する際は、雇用保険の資格喪失手続きを行い、必要に応じて離職票を交付します。この手続きは、退職者が失業給付を受けるために必要であり、また後述する「外国人雇用状況届出」も兼ねることができる重要な手続きです。
退職日の翌日から10日以内にハローワークへ届け出る必要があるため、スケジュール管理には十分注意しましょう。
雇用保険の資格喪失手続きでは、以下の書類をハローワークへ提出します。
- 雇用保険被保険者資格喪失届(在留カード番号記載様式=様式第4号)
- 離職証明書(離職票が必要な場合に提出する書類)
外国人労働者の雇用保険資格喪失手続きでは、在留カード番号の記載が必須になりますので、必ず確認するようにしましょう。この届出により、入国管理局への別途届出が原則不要になります。詳しくは「外国人雇用状況届出」のセクションで解説します。
退職する外国人労働者が「離職票は不要」と伝えてきた場合でも、後日「やはり必要」となるケースが非常に多いため、基本的には離職証明書も併せて提出することを強く推奨します。
提出期限としては「退職日の翌日から起算して10日以内」となっており、事業所を管轄するハローワークへ提出する形となります。
なお、ハローワークへの提出時には、以下の書類を添付する形となりますので、事前に準備しておきましょう。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 出勤簿又はタイムカード
- 退職辞令発令書類
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 離職理由が確認できる書類(退職届など)
- 離職証明書(離職票が必要な場合)
社会保険(健康保険・厚生年金)の資格喪失手続き
外国人労働者が退職した際は、社会保険の資格喪失手続きも必要です。
期日は「退職日の翌日から5日以内」に事業所を管轄する年金事務所、または加入している健康保険組合が提出先となっています。雇用保険の資格喪失手続き(10日以内)よりも期限が短いため、優先的に対応する必要があります。
健康保険と厚生年金保険の資格喪失は、通常一体型の届出様式で提出します。日本年金機構のウェブサイトから様式をダウンロードできます。
届出の際には、退職者から回収した健康保険証(被保険者証)を添付して提出します。扶養家族がいる場合も全て回収が必要です。もし、保険証を紛失している場合は、被保険者証回収不能・滅失届を提出する形となります。
社会保険に関しては、外国人特有の注意すべき点があります。
まず、外国人労働者が母国に帰国する場合、厚生年金保険の脱退一時金を請求できる可能性がある点です。資格喪失手続きとは別に、退職者本人が日本を出国後に申請する制度ですが、企業側から退職者に情報提供しておくと親切です。
また、退職後は健康保険の資格を失うため、以下のいずれかの手続きが必要であることを伝えましょう。
- 国民健康保険への加入
- 健康保険の任意継続(退職後20日以内に申請)
- 家族の健康保険の被扶養者になる
特に再就職まで期間が空く場合や、帰国準備で日本に滞在する場合は、無保険期間を作らないよう注意が必要です。
源泉徴収票の交付
源泉徴収票とは、「1年間に企業からどれくらいの給料が支払われ、所得税をいくら納めたか」が記載された書類のことを指します。
源泉徴収票が必要になるタイミングとしては大きく3つ想定されます。
まず、日本国内で転職する場合、新しい勤務先で年末調整を受けるために、前職の源泉徴収票の提出が求められます。
また、年の途中で退職し、年末まで再就職しなかった場合や、複数の勤務先で働いていた場合は、本人が確定申告を行う必要があります。この際、源泉徴収票に記載された情報をもとに申告を行います。特に外国人労働者の場合、税金の還付を受けられるケースも多いため、確定申告の重要性を伝えておくと親切です。
最後に、母国に帰国する外国人労働者の中には、帰国後に日本での所得を母国の税務当局に報告する必要がある方もいます。その際、源泉徴収票が証明書類として必要になる場合があります。
源泉徴収票は所得税法によって事業主に交付が義務付けられています。そのため仮に本人から請求されなくとも、退職後1か月以内に交付することが求められる点は留意しましょう。
住民税の処理(特別徴収から普通徴収への切替)
住民税は、会社が従業員へ支払う給与から天引きし市町村に納付する「特別徴収」が原則とされています。
そのため、外国人労働者が退職すると特別徴収ができなくなるため、市町村に届け出をしなければなりません。
届け出ることで、退職者あてに住民税の通知が郵送され、退職者自身で住民税を納入することになります。
その後、就職して再度特別徴収になる場合は、新たな就業先が特別徴収継続の届出を提出します。
- 提出書類:給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
- 提出期限:退職後すみやかに
- 提出先:退職時の居住地の市町村
- 提出方法:持参または郵送
前年中に転居している場合は転居前と後の2カ所に届ける必要や、1月から5月に退職する場合には住民税は一括徴収する必要があるので注意しましょう。
退職証明書の交付
企業側は外国人社員に退職証明書を交付する必要があります。
外国人労働者が転職する場合、出入国在留管理庁に対して、以下のような在留資格の手続きを行います。
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 就労資格証明書交付申請
これらの手続きを実施するための必要書類として、退職証明書が求められるのです。
そのため外国人労働者が退職後帰国する場合を除いて、忘れずに交付するようにしましょう。
なお、退職証明書には決まった様式がありませんので、一般的なテンプレートを編集する形で問題ないでしょう。
外国人雇用状況届出(ハローワーク)
外国人労働者を雇用する企業には、法令に基づき、雇入れ及び離職の際に「外国人雇用状況の届出」が義務付けられています。
この届出は、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援を目的としたもので、退職時には必ず届け出なければなりません。
外国人雇用状況の届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。対象者としては、「在留資格「公用」「外交」以外、すべての外国人労働者」となっています。外国人労働者の退職手続きにおいて、特に重要な届出の一つですので、必ず期限内に対応しましょう。
なお、雇用保険被保険者であれば、外国人雇用状況届出は「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出と兼ねることができますので、特段手続きは必要ありません。もし、雇用保険被保険者ではない場合は、外国人雇用状況届出書(様式第3号)をハローワークに退職月の翌月末日までに提出する必要があります。
【本人側】退職時に外国人本人が実施する手続きは?
ここからは、本人側の退職時の手続きについて整理していきましょう。
離職票と源泉徴収票の受け取り
外国人労働者が退職する際は、企業から交付される離職票と源泉徴収票を必ず受け取る必要があります。
離職票は失業給付の申請に必要となり、源泉徴収票は転職先での年末調整や確定申告で使用します。特に帰国する場合や転職する場合は、これらの書類がないと手続きが進められないため、退職時に確実に受け取り、大切に保管するようお伝えしましょう。
所属(契約)機関に関する届出
外国人労働者本人が行うべき重要な手続きの一つが、所属機関に関する届出です。
この手続きは、外国人労働者が退職や転職をした際に、出入国在留管理庁(入国管理局)に対して届け出るもので、退職した外国人本人が自ら行う義務があります。
「所属機関」とは、外国人の方を受け入れている、または受け入れようとする日本の公私の機関等を指します。具体的には、以下のような機関が該当します。
- 企業(株式会社、有限会社、個人事業主など)
- 学校などの教育機関
- 研究機関
- その他の受入れ機関
外国人労働者にとっては、勤務先の会社が所属機関に該当します。
所属機関に関する届出が必要となるのは、「退職」「転職」「所属機関の名称や所在地が変更された場合」です。離職などの事由が生じた日から14日以内に行う義務があるので、退職が決まったら速やかに手続きを進める必要があります。
この届出を怠ると、以下のような不利益が生じる可能性があります。
- 在留資格の更新が不許可になる可能性:在留資格の更新申請時に、届出義務を履行していないことが判明すると、更新が不許可になるリスクがあります。
- 在留資格の取消対象になる可能性:正当な理由なく届出を行わなかった場合、在留資格が取り消される可能性もあります。
- 罰金刑の可能性:虚偽の届出を行った場合や、正当な理由なく届出を怠った場合は、20万円以下の罰金が科される可能性があります。
直接入管の窓口へ手続きをするだけではなく、オンラインでも申請が可能になっていますので、受け入れ企業としては、本人へ上記内容をお伝えしてあげましょう。
在留資格の更新・変更
続いて必要なのが、在留資格の期間更新や変更のための手続きです。
転職予定にも関わらず残りの在留期間が短くなっている場合、在留期間更新許可申請を実施する必要があります。
加えて、転職後の職種が、現在外国人労働者が保有している在留資格で許可された範囲外の職種である場合、在留資格変更許可申請をしなければなりません。
注意点として、特定技能や特定活動46号など、職種の有無に関わらず、転職時に必ず在留資格変更許可申請をしなければならない在留資格も存在します。
これらの申請については、基本的に外国人労働者本人が対応すべきものではありますが、雇用する企業が代理人として申請することもでき、多くの場合企業側も手伝うことになるでしょう。
また転職を伴う在留期間更新を実施する場合、事前に就労資格証明書交付申請をしておく方がスムーズに手続きを進めることができます。
失業手当(失業保険)の申請
失業手当(失業給付金)の申請は、雇用保険に加入していた外国人労働者が対象となる手続きです。すべての退職者が受給できるわけではありませんが、条件を満たせば、再就職までの生活をサポートする給付金を受け取ることができます。
原則として、離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが必要です。ただし、倒産・解雇など会社都合での離職の場合は、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算6か月以上あれば受給できます。
失業給付金は、働く意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、就職できない状態にある方が対象です。そのため、以下のような場合は受給できません。
- すぐに母国へ帰国する予定がある
- 病気やけがで働けない状態
- 妊娠・出産・育児ですぐに働けない
- 学業に専念する予定
また、ハローワークで求職の申込みを行い、積極的に求職活動をする必要がありますので、単に給付金を受け取るだけでなく、再就職に向けた活動が求められます。
健康保険の切り替え手続き
退職すると、会社の健康保険の資格を失うため、外国人労働者本人が新しい健康保険に切り替える手続きが必要です。
選択肢は主に3つあります。国民健康保険への加入(退職後14日以内に市区町村役場で手続き)、健康保険の任意継続(退職後20日以内に申請、最長2年間継続可能)、または家族の健康保険の被扶養者になる方法です。
すぐに転職する場合は転職先の健康保険に加入しますが、再就職まで期間が空く場合や帰国準備で日本に滞在する場合は、無保険期間を作らないよう速やかに手続きを行いましょう。

母国に帰国する場合の手続き
こちらに記載の内容は、外国人労働者が退職後に母国に帰国する場合に該当してきます。
脱退一時金の手続き
まず、国民年金や厚生年金の脱退一時金を請求することができます。
脱退一時金とは日本国籍を持っていない外国人労働者が、老齢年金の受給資格となっている10年を満たさずに帰国する場合に、既に納めている年金保険料の一部を返金支給してもらう制度です。
もし一時的に帰国した後、再び来日して働く予定がある場合は日本における年金受給資格を満たせる可能性があるため、脱退一時金の請求手続きはする必要がありません。
帰国した後、再度日本で暮らことがないのであれば脱退一時金の請求をしておく方がよいでしょう。
脱退一時金に関しては、「【外国人の脱退一時金とは】概要や種類、手続きの方法をわかりやすく解説」でも解説していますので、あわせてご覧ください。
住民税の支払い
住民税は、1月1日の居住地の市町村で、前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。つまり、外国人が年度の途中で帰国しても、1月1日の時点で住民登録があれば、その年の住民税を納める義務があります。
外国人労働者は、退職後に帰国する場合、残りの住民税を一括して給与や退職金から徴収してもらうことができます。(退職が1〜5月は、希望の有無に関わらず一括徴収されます)
もし、出国までの間に住民税を納めることができない場合は、日本に居住する方の中から納税管理人を選任し、残りの住民税の支払いを実施する必要が出てきます。詳しくは、こちらの総務省HPをご覧ください。
銀行口座の解約
忘れがちなのが、銀行口座の解約です。仮に銀行口座の預金が0円になっていたとしても口座解約手続きが必要です。
口座の解約は、各行の窓口に通帳・キャッシュカード・在留カード・印鑑などを持参する必要があります。
解約せずに10年以上(ゆうちょ銀行は5年)放置されると、預金は休眠預金になり、利用できなくなる可能性もあります。
ただ注意しなくてはいけないのが、携帯、水光熱などの公共料金、クレジットカードの利用料金...など、引き落としの予定がある場合、引き落とし前に銀行口座を解約しないように注意しましょう。
料金が未払いのままになると、将来日本でクレジットカードの申込や、住宅ローンの申込、携帯電話の契約ができなくなる可能性があります。
住民票の転出届
今後日本に暮らす予定のない外国人は、帰国前に、帰国日を証明する書類(航空券など)、在留カード、パスポートなどの身分証明書を持っていき、居住地の市・区役所に転出届の手続きを行う必要があります。
住民票転出届の手続き期間は居住地により多少異なりますが、帰国する日の約2週間前から提出が可能です。
転出届の手続きを行わずに帰国した場合、帰国後も住民税や年金、国民健康保険料を請求されたり、年金の脱退一時金を受け取れなかったりする可能性があるので、帰国前に必ず手続きを行いましょう。
同時に、マイナンバーカードやマイナンバー通知カードの返却も実施するようにしましょう。マイナンバー自体は、新しい番号が付与されることはないので、もし将来的に再度日本へ来日することが予想される場合は、マイナンバーカードが返却されますので、大切に保管しておく必要があります。
退去など生活全般の手続き
その他、諸々の生活に関わる解約系の手続きを全て実施しておく必要があります。
①賃貸契約(住居)の解約
日本の賃貸借契約は、一般的に、退去日の1~2ヶ月前に退去告知をする必要があるため、帰国が決まった際は速やかに退去予定日を管理会社に連絡をしましょう。
退去告知が遅れた場合、住んでいなくても家賃の請求をされる場合があります。
②電気・水道・ガスの停止
電気、水道、ガスの使用停止の手続はインターネットや電話で簡単にできます。
停止申込みの際に「お客さま番号」が必要なことが多いため、用意しておくと良いでしょう。
また、立ち会いが必要な場合もあるため、退去日が決まったら速やかに停止の手続きをしましょう。
③携帯電話やインターネットの解約
携帯電話、スマホ、インターネットの解約手続きも必要です。
口座引き落としやクレジットカード支払いになっている場合、それぞれの解約前に利用料金の精算を忘れないよう注意しましょう。
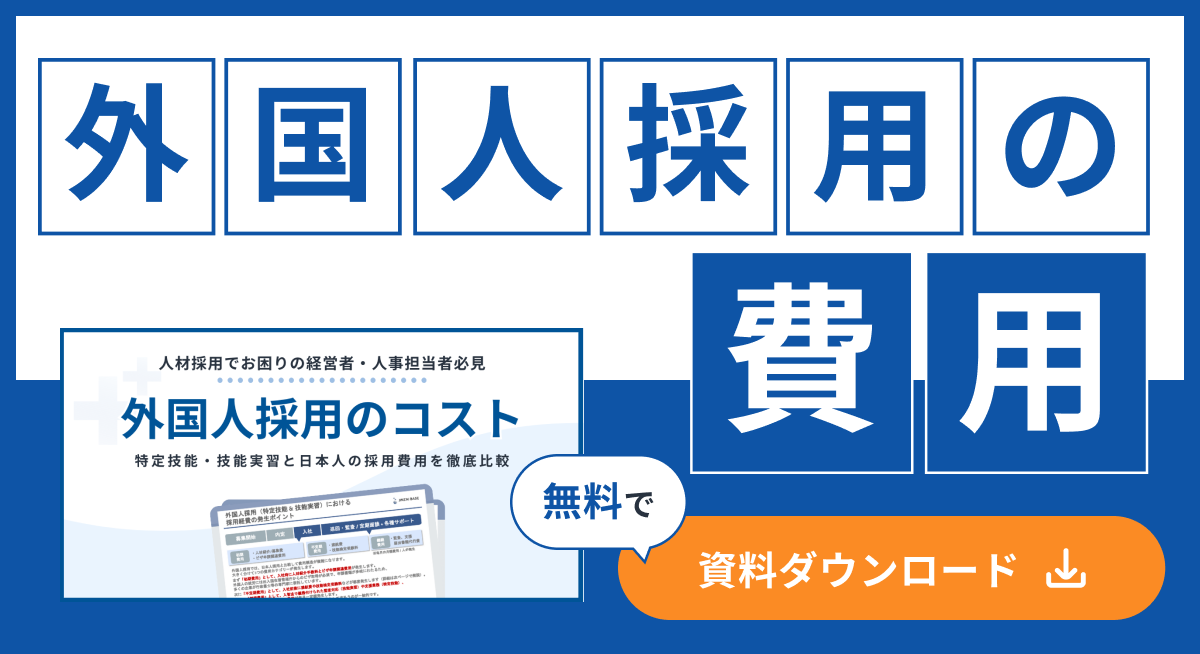
特定技能外国人が退職する場合の特別な対応
ここからは、在留資格「特定技能」を有する外国人が退職する場合の手続きを見ていきます。特定技能については、他の在留資格と比較したときに、少し異なる特別な手続きが必要なので、注意しましょう。
支援計画の終了と報告義務
特定技能外国人を雇用する企業は、1号特定技能外国人支援計画に基づいて各種支援を実施する義務があります。
外国人が退職する場合、この支援計画は終了となりますが、企業には出入国在留管理庁への報告義務があります。具体的には、特定技能外国人の受入れ困難に係る届出を、事由発生日(退職日)から14日以内に提出する必要があります。
また、支援実施状況に係る届出として、退職までに実施した支援内容を四半期ごとに報告しなければなりません。これらの届出を怠ると、今後の特定技能外国人の受入れに影響が出る可能性があるため、期限内に確実に報告しましょう。
届出はオンラインまたは地方出入国在留管理局の窓口で行うことができます。
登録支援機関との連携
特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託している企業の場合、外国人が退職する際は登録支援機関との連携が重要になります。
まず、退職が決まった時点で速やかに登録支援機関に連絡し、退職日や理由などの情報を共有しましょう。登録支援機関は、委託契約に基づいて退職に関する各種支援を行います。
また、支援委託契約の終了手続きも必要です。契約内容によっては、退職時の精算や最終報告が求められる場合があります。
登録支援機関は、出入国在留管理庁への届出書類の作成支援や、転職を希望する外国人への情報提供なども行います。企業単独で対応するよりも、登録支援機関と密に連携することで、スムーズかつ適切な退職手続きが可能になるでしょう。
登録支援機関については「登録支援機関の役割とは?特定技能外国人への支援内容や選び方を徹底解説!」の記事もぜひ併せてご覧ください。
転職支援について
特定技能外国人が退職後も日本で働き続けることを希望する場合、企業には転職支援を行う努力義務があります。
具体的には、他の受入れ機関に関する情報提供や、ハローワーク等の公的職業紹介機関の利用案内などが該当します。特定技能外国人が円滑に転職できるよう、可能な範囲でサポートすることが求められます。
また、登録支援機関に支援を委託している場合は、登録支援機関が転職先の紹介や求人情報の提供を行うケースもあります。
転職支援を適切に行うことは、特定技能外国人本人のキャリア継続を支えるだけでなく、企業の社会的責任を果たすことにもつながります。今後も特定技能外国人を受け入れる予定がある企業にとっては、誠実な対応が信頼構築にも重要です。
特定技能外国人の転職については「【特定技能における転職】転職ができる条件や手続きなどをまとめて解説」の記事もご覧ください!

外国人が退職する際の注意点は?
外国人労働者の退職に伴う手続きについてお話してきたところで、最後に注意点について簡単に確認しておきましょう。
退職届の回収をする
こちらは、日本人の場合と同様ですが、自己都合退職の場合は、必ず外国人本人から退職届を回収するようにしておきましょう。
過去、自分から退職を申し出たのに、転職活動がうまくいかず、別の在留資格へ変更するために「会社都合で解雇された」と入管に申し出たりする方がいらっしゃいました。
あまりないケースではありますが、コンプライアンス的にも、退職者(日本人も同様)からは必ず退職届は回収しておいた方が良いでしょう。
退職後、3ヶ月で就労系在留資格(ビザ)が失効する可能性がある
就労系の在留資格の場合、その名の通り「就労すること」が目的の在留資格となります。
そのため、自己都合での退職後、3ヶ月以上無職の状態が続いたり、何も活動していないと判断された場合は、就労ビザが失効する可能性があります。
退職した外国人は、次の職を見つけるのに3ヶ月のリミットがあるという点は、受け入れ企業側でも把握しておきましょう。
退職後はアルバイトはできる?
現在保有する在留資格の活動範囲内であれば、アルバイトは可能になります。ただし、「技術・人文知識・国際業務」などの場合は、在留資格で認められた範囲外の業務(例えば、配達員やコンビニのレジ打ちなど)は基本的に認められませんので、注意が必要です。
こういった行為をしていると、仮に次の職場が見つかったとしても、入管から在留状況が不良と判断され、ビザ更新ができなくなってしまう可能性があります。
一方で、会社都合での解雇などを理由に退職した場合は、生計を立てるために、資格外活動が認められるケースがあります。また、転職活動を希望する場合は、在留期間が到来したとしても、「特定活動」という別のビザへ変更し、在留が認められるケースもあります。
まとめ
今回は外国人労働者の退職手続きについてお話してきましたが、いかがでしたか。外国人労働者を雇用している場合、どこかのタイミングで退職の手続きをする必要が出てくるでしょう。
その際は是非この記事を参考にしていただければ幸いです。
当社は、外国人に特化した人材紹介事業を行っております。特に、特定技能制度を利用した外国人の採用をご検討されている方や技術・人文知識・国際業務などの高度人材の募集をご検討されている企業様は、ぜひこちらのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。








.jpeg)









