製造業においてDXの必要性が叫ばれる一方で、「なかなか進まない」という声が多く聞かれます。経済産業省の調査によれば、中小製造業でDXに着手している企業は依然として2〜3割程度にとどまっており、大企業との格差が広がっています。
DXが進まない理由は何なのでしょうか? そして、どうすれば製造業のDXを成功させることができるのでしょうか?
本記事では、製造業DXが進まない5つの理由を詳しく解説するとともに、人材不足という最大の課題に対する具体的な解決策をご紹介します。特に、外国人材の活用という新たな選択肢についても触れていますので、人手不足とDX推進の両方でお悩みの製造業経営者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
製造業DXとは?現状と必要性
製造業を取り巻く環境が大きく変化する中、DXの重要性が高まっています。まずは基礎知識を確認しましょう。
製造業DXの定義と目指すべき姿
製造業DXとは、IoTやAI、クラウドなどのデジタル技術を活用して、製造プロセス全体を変革する取り組みです。
単なるIT化やデジタル化にとどまらず、データに基づいた意思決定により、生産性向上や新たな価値創造を実現することを指します。目指すべき姿は、リアルタイムでの生産状況の可視化、予知保全による設備稼働率の向上、需要予測の精度向上などを通じて、競争力のある製造体制を構築することです。
DXは業務効率化だけでなく、ビジネスモデルそのものを革新する可能性を秘めているのです。
日本の製造業DX推進状況
ものづくり白書によれば、製造業におけるデジタル技術を活用した業務改善は、工程によって取り組み状況に差が見られます。

「製造」「生産管理」「事務処理」「受注・発注・在庫管理」では4割強から5割強の企業が実施している一方、「企画・開発・設計」「品質管理」では3割程度にとどまっています。
特に企業規模による格差が顕著で、従業員300人以上の企業では製造工程で67%が取り組んでいるのに対し、100人以下の企業では39%と大きな開きがあります。
また、全体の約2割の企業はデジタル技術を活用した業務改善を全く行っておらず、中小製造業を中心にDX推進の遅れが課題となっています。
DXが遅れることで生じる3つのリスク
製造業DXの遅れは、企業経営に深刻な影響をもたらします。
第一に、国際競争力の低下です。デジタル化が進む海外企業との生産性格差が広がり、価格競争力や納期対応力で劣位に立たされます。
第二に、人材不足の深刻化です。アナログな業務環境は若手人材の採用を困難にし、技術継承も属人化したまま進まなくなります。
第三に、ビジネス機会の喪失です。顧客ニーズの多様化やカスタマイゼーション要求に柔軟に対応できず、新規受注の獲得が難しくなります。DXの遅れは単なる効率性の問題ではなく、企業の存続に関わる重要課題といえます。
製造業DXが進まない5つの理由
製造業でDXの必要性は認識されているものの、実際の推進は容易ではありません。多くの企業が直面する5つの課題について詳しく見ていきましょう。
【理由1】経営層と現場の認識ギャップ
DX推進において最も大きな障壁となるのが、経営層と現場との認識のずれです。
経営層は「競争力強化」や「業務効率化」といった大きなビジョンを掲げる一方、現場では「今の作業を覚えるだけで精一杯」「システムが増えて逆に手間が増える」といった不安や抵抗感が生まれます。特に長年培ってきた作業方法を変更することへの心理的ハードルは高く、「今のやり方で問題ない」という意識が根強く残っています。
経営層が投資判断を下しても、現場の協力が得られなければDXは形骸化してしまいます。この温度差を解消せずに進めると、導入したツールが使われないまま放置される事態を招きます。
【理由2】DX推進人材の圧倒的不足
製造業において最も深刻な課題が、DXを推進できる人材の不足です。
デジタル技術に精通し、かつ製造現場の実情を理解している人材は極めて限られています。経済産業省の調査では、IT人材不足は2030年には最大79万人に達すると予測されており、製造業も例外ではありません。社内でDX人材を育成しようにも、日常業務に追われて教育の時間が確保できない企業が大半です。

また、外部からIT人材を採用しようとしても、製造業は他業界と比べて魅力的な待遇を提示しにくく、優秀な人材の獲得競争で不利な立場に置かれています。人材がいなければ、どれだけDXの重要性を認識していても実行に移せません。
【理由3】初期投資とコスト回収への不安
DX推進には多額の初期投資が必要となり、特に中小製造業にとっては大きな負担となります。システム導入費用だけでなく、社員教育コストや運用保守費用も継続的に発生します。
さらに、投資対効果が見えにくいことも課題です。設備投資であれば生産量の増加という明確な成果が見込めますが、DXの効果は可視化しにくく、経営判断が難しくなります。「投資したのに期待した効果が得られなかった」という失敗事例を耳にすると、慎重姿勢が強まります。
加えて、景気変動や受注状況の不透明さから、長期的な投資計画を立てにくい企業も多く、結果として「今はまだ早い」とDX導入が先送りされる悪循環が生まれています。
【理由4】既存システム(レガシーシステム)との統合課題
多くの製造業では、長年使用してきた基幹システムや生産管理システムが稼働しています。
これらのレガシーシステムは業務に深く組み込まれており、簡単には刷新できません。新しいデジタルツールを導入しようとしても、既存システムとの連携ができず、データが分断されてしまうケースが頻発します。システム間でデータのやり取りができなければ、手作業での転記が必要となり、かえって業務負担が増加します。
また、古いシステムの仕様書が残っていない、開発した業者が既に存在しないなど、技術的な制約も大きな障壁です。システム全体を刷新するには莫大なコストと時間がかかるため、現状維持を選択せざるを得ない企業が少なくありません。
【理由5】アナログ業務からの脱却が困難
製造現場では依然として紙の作業指示書、手書きの日報、ホワイトボードでの進捗管理など、アナログな業務が根強く残っています。長年慣れ親しんだ方法を変えることへの抵抗感は強く、特にベテラン従業員ほど「今のやり方で十分」という意識が強い傾向にあります。
デジタルツールの操作に不慣れな従業員にとっては、新しいシステムの習得自体が大きな負担となります。また、製造現場特有の環境も課題です。油や粉塵が舞う現場ではタブレットやPCが使いにくく、手袋をしたままではタッチパネルの操作ができないなど、物理的な制約もあります。
こうした現場の実情を考慮せずにデジタル化を進めても定着せず、結局元のアナログ業務に戻ってしまうケースが多発しています。
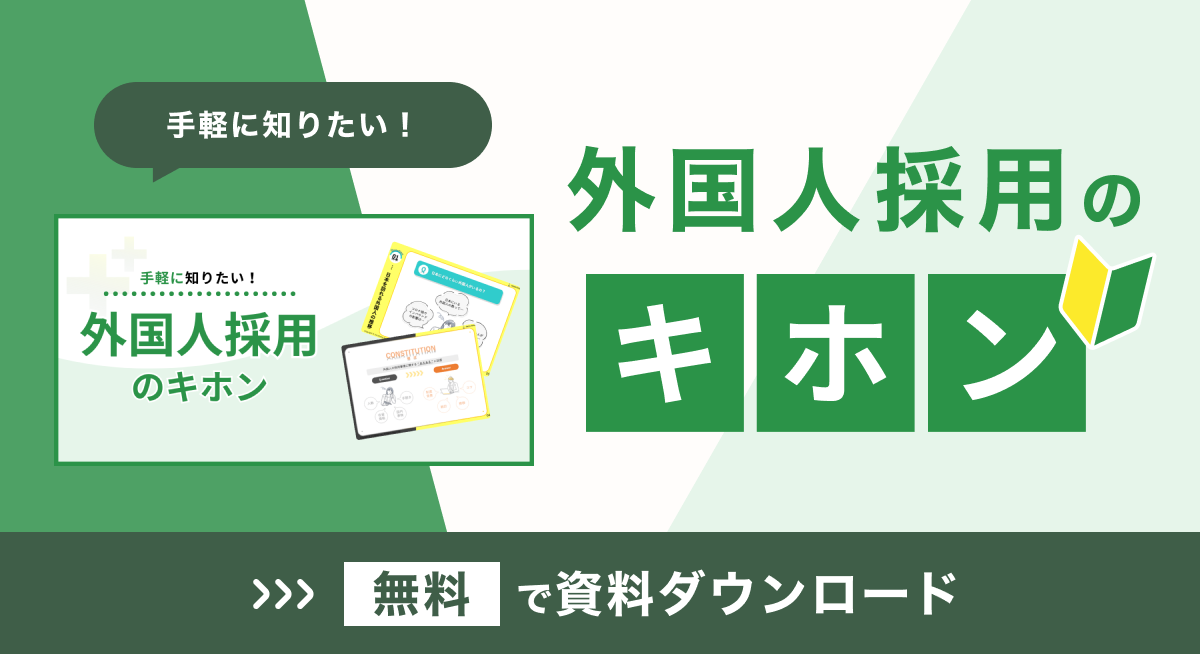
DX人材不足が製造業に与える深刻な影響
前章で見たように、DX推進人材の不足は製造業が直面する最大の課題の一つです。この人材不足が企業経営にどのような影響を及ぼしているのか、具体的に見ていきましょう。
IT人材が確保できない製造業の現状
製造業におけるIT人材の確保は年々困難になっています。
情報処理推進機構(IPA)の「DX動向2025」によれば、DXを推進する人材の量について「やや不足している」「大幅に不足している」と回答した日本企業は85.1%に達しており、米国(23.8%)やドイツ(44.6%)と比較しても突出して高い水準です。

この状況は2022年度以降ほぼ改善が見られず、慢性的な人材不足が続いています。特に地方の中小製造業では、都市部のIT企業やWeb系企業との採用競争に勝てず、優秀な人材を獲得できない状況が続いています。
新卒採用でも、製造業はIT業界と比べて初任給や労働環境の面で見劣りすることが多く、デジタル人材からの応募が集まりにくい傾向にあります。
人材不足で先送りされるDX投資
DX人材が確保できないことで、多くの製造業企業がデジタル投資を先送りせざるを得ない状況に陥っています。
システムやツールを導入しても、運用できる人材がいなければ宝の持ち腐れとなるため、経営層は投資判断を躊躇します。実際に「DXの必要性は理解しているが、人がいないので着手できない」という声は製造業界全体で広がっています。この悪循環により、競合他社がDXで生産性を向上させる中、自社だけが取り残されていくリスクが高まります。
また、人材不足を理由に小規模なデジタル化すら進められず、業務効率化の機会を逃し続けることで、現場の負担はさらに増大します。結果として、人材不足がさらなる人材流出を招くという負のスパイラルに陥る企業も出てきています。
技術継承とDX化の両立という課題
製造業では熟練技術者の高齢化が進み、技術継承が喫緊の課題となっています。
ベテラン従業員の持つ暗黙知やノウハウをデジタル化して次世代に継承することがDXの重要な目的の一つですが、その実行には高度なIT知識と現場理解の両方が必要です。
しかし現実には、製造技術に精通した人材とデジタル技術に精通した人材が別々に存在し、両者をつなぐ人材がいないという問題が生じています。技術者は「自分の技術をどうデータ化すればよいかわからない」、IT担当者は「現場の何をデジタル化すべきかわからない」という状態で、技術継承のDX化が進みません。
このままでは、貴重な技術が失われるだけでなく、DX化の機会も同時に失われてしまいます。
製造業DXを推進するための3つの解決策
DX推進における課題は多岐にわたりますが、適切なアプローチを取ることで着実に前進できます。ここでは、実践的な3つの解決策をご紹介します。
【解決策1】小規模プロジェクトからスタートする
DX推進で失敗する企業の多くは、最初から大規模なシステム刷新を目指して挫折しています。
成功のカギは「スモールスタート」です。
まずは特定の工程や部署に限定して、小規模なデジタルツール導入から始めましょう。例えば、紙の日報をタブレット入力に変える、在庫管理だけをクラウド化するなど、限定的な範囲で成果を実感できる取り組みが効果的です。小さな成功体験を積み重ねることで、現場の抵抗感が薄れ、経営層も次の投資判断がしやすくなります。
また、失敗しても被害を最小限に抑えられるため、リスク管理の観点からも有効です。PDCAサイクルを素早く回しながら、段階的に拡大していくアプローチが現実的といえます。
【解決策2】外部パートナー・ベンダーとの連携
社内にDX人材が不足している場合、外部の専門家やベンダーとの連携が有効な選択肢となります。
ITコンサルタントやシステムインテグレーターは、製造業のDX事例に精通しており、自社に適したソリューションを提案してくれます。
重要なのは、丸投げするのではなく、社内にもDXの知見を蓄積していく姿勢です。外部パートナーと協働しながら、徐々に社内メンバーがデジタル技術に習熟していく体制を構築しましょう。また、同業他社とのDXコンソーシアムに参加することで、情報交換や共同でのツール開発も可能になります。外部の力を借りつつ、長期的には内製化を目指すバランスが大切です。
【解決策3】多様な人材の活用でDX推進体制を強化
DX推進において最も重要なのは、適切な人材を確保することです。しかし、前述の通り日本国内でのIT人材不足は深刻で、従来の採用手法だけでは限界があります。
そこで注目されているのが、多様な人材の活用です。社内の若手人材を積極的に登用してデジタルネイティブ世代の感覚を取り入れる、女性や中途採用者など多様なバックグラウンドを持つ人材を活用する、さらには外国人材という選択肢も有効です。
特に外国人IT人材は、母国で高度なデジタル教育を受けており、即戦力として活躍できる可能性が高いです。また、製造現場での人手不足解消と並行して、DX推進にも貢献できる外国人材の活用は、人材戦略の観点から合理的といえます。
多様な視点を持つ人材がチームに加わることで、固定観念にとらわれない革新的なDX推進が期待できます。
DX人材確保の新たな選択肢:外国人IT人材の活用
日本のIT人材不足が85%を超える中、外国人IT人材の採用は現実的な選択肢となっています。
特にベトナム、インド、フィリピンなどのアジア諸国では、質の高いIT教育が行われており、プログラミングやデータ分析のスキルを持つ人材が豊富で、オフショア開発の拠点としても注目を集めています。外国人IT人材を活用するメリットは、即戦力として採用できる点に加え、日本人IT人材と比較して採用競争が緩やかで、相対的に採用しやすいという点があります。
また、グローバルな視点を持つ外国人材が加わることで、海外展開を視野に入れたDX戦略の立案にもつながります。言語面の不安を感じる企業も多いですが、IT分野では英語が共通言語として機能しやすく、また日本語能力試験N2~N3レベルの日本語力を持つ人材も増えています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を活用すれば、システムエンジニアやデータアナリストとしての雇用が可能です。
ぜひ「技術・人文知識・国際業務とは?技人国ビザの職種一覧や許可/不許可事例も!」の記事も併せてご覧ください。

特定技能「製造業」での外国人材受け入れメリット
外国人IT人材の採用と並行して検討したいのが、製造現場での特定技能外国人の活用です。
DXを推進してシステムを整備しても、実際に製造を行う現場の人手が不足していては意味がありません。むしろ、技術継承や品質維持のためには、現場での実務を担う人材確保が不可欠です。しかし、日本人の製造業離れが進む中、現場作業員の採用は年々困難になっています。
特定技能「製造業」では、機械加工、溶接、塗装、鋳造などの分野で外国人材の雇用が可能です。多くは日本語能力N4程度で、現場での実作業を担う人材として受け入れられます。デジタル化によって効率化された業務フローの中で、実際の製造作業や品質チェック、設備オペレーションなどの実務を遂行する役割を担います。
DX推進と現場人材確保は表裏一体の課題です。外国人IT人材でDX体制を構築し、特定技能外国人で製造現場の人手を確保する。この両輪での外国人材活用が、製造業の持続可能な成長につながる現実的な解決策といえるでしょう。
ぜひ「在留資格「特定技能」とは?技能実習との違いも含めてわかりやすく解説!」の記事も併せてご覧ください。

製造業DXを成功させる5つのステップ
DX推進を成功に導くためには、計画的なステップを踏むことが重要です。ここでは、多くの製造業で成果を上げている実践的な5つのステップをご紹介します。
ステップ1:現状分析と課題の可視化
DX推進の第一歩は、自社の現状を正確に把握することです。
どの工程にどれだけの時間がかかっているのか、どこでミスが発生しやすいのか、データに基づいて可視化しましょう。現場へのヒアリングや業務フローの図式化を通じて、ボトルネックとなっている作業を特定します。この段階では、経営層の視点だけでなく、実際に作業を行う現場従業員の意見を丁寧に聞き取ることが重要です。
課題が明確になれば、DXで解決すべき優先順位も自然と見えてきます。現状分析を怠ると、的外れなシステム導入につながり、投資が無駄になるリスクがあります。
ステップ2:DXビジョンと目標の明確化
現状分析ができたら、次にDXで実現したい将来像を明確にします。
「3年後に生産性を20%向上させる」「不良品率を半減させる」など、具体的で測定可能な目標を設定しましょう。重要なのは、経営層だけでなく現場も含めた全社でビジョンを共有することです。「なぜDXが必要なのか」「DXによって現場の働き方がどう改善されるのか」を丁寧に説明し、従業員の理解と協力を得ることが成功の鍵となります。
目標が曖昧なまま進めると、途中で方向性を見失い、プロジェクトが頓挫する原因になります。
ステップ3:推進チームの組成と人材配置
DXを組織的に推進するため、専任のプロジェクトチームを編成します。
理想的なチーム構成は、経営層からの推進責任者、IT知識を持つメンバー、そして現場を熟知した従業員の混成チームです。外部のITコンサルタントや、前述した外国人IT人材を加えることも効果的です。
重要なのは、特定の個人に負担が集中しないよう、役割分担を明確にすることです。また、チームメンバーには一定の権限を与え、迅速な意思決定ができる体制を整えましょう。人材が不足している場合は、外部パートナーとの連携や外国人材の活用も検討すべきです。
ステップ4:優先順位をつけたツール導入
すべての業務を一度にデジタル化しようとすると、現場が混乱し失敗します。
ステップ1で可視化した課題の中から、「効果が大きく、導入が比較的容易なもの」を優先的に選びましょう。例えば、紙の作業日報をタブレット入力に変える、在庫管理をクラウド化するなど、限定的な範囲から始めます。小さな成功体験を積み重ねることで、現場の抵抗感が薄れ、次のステップへの協力も得やすくなります。
ツール選定では、既存システムとの連携可能性や、操作の簡便性を重視しましょう。高機能でも使いこなせなければ意味がありません。
ステップ5:PDCAによる継続的改善
DXは一度導入して終わりではなく、継続的な改善が不可欠です。
導入後は定期的に効果測定を行い、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のサイクルを回し続けます。「当初の目標は達成できているか」「新たな課題は発生していないか」を検証し、必要に応じてツールの設定変更や運用ルールの見直しを行います。現場からのフィードバックを積極的に収集し、使いにくい点があれば速やかに改善することで、システムの定着率が高まります。
また、成功事例は社内で共有し、他部署への横展開を図ることで、DXの効果を全社に広げていきましょう。
製造業DX推進における外国人材活用のポイント
これまで見てきたように、DX推進と人材確保は製造業における喫緊の課題です。ここでは、外国人材を活用する際の具体的なポイントと注意点について解説します。
IT系外国人材の採用で得られる効果
外国人IT人材の採用は、単なる人手不足の解消以上の効果をもたらします。
第一に、即戦力としての活躍が期待できます。ベトナムやインドなどのIT教育先進国出身者は、プログラミングやデータ分析のスキルを既に習得しており、研修期間を短縮できます。
第二に、多様な視点がイノベーションを促進します。異なる文化背景を持つ人材が加わることで、固定観念にとらわれない新しいアイデアが生まれやすくなります。
第三に、グローバル展開への布石となります。外国人材とのコミュニケーションを通じて、社内の英語対応力が向上し、将来的な海外進出の基盤が整います。また、比較的若い世代が多いため、長期的な人材育成の観点からも有効です。
製造業で活躍する特定技能技能外国人の事例
実際に製造現場で外国人材が活躍している事例をご紹介します。
埼玉県でバケットコンベアの製造・販売を手掛ける株式会社翔和様では、日本人採用が困難な状況が続いていました。将来的な東南アジア展開も視野に入れ、ベトナム人技能実習生の受け入れからスタートし、現在では特定技能外国人を中心とした雇用体制を構築されています。
同社の現場担当者からは「外国人社員はなくてはならない存在」との声をいただいており、技術習得の意欲が高く、真面目に業務に取り組む姿勢が評価されています。製造現場での特定技能外国人の受け入れ事例は年々増加しており、人手不足解消の有力な選択肢となっています。
DX推進のためのIT人材確保に加え、製造現場での人材不足にお悩みの企業様は、外国人材の活用も含めた総合的な人材戦略をご検討されることをお勧めします。
インタビュー記事「【事例インタビュー】日本人はいらないと現場担当者が言うくらい、外国人社員はハングリー精神が旺盛です」もぜひご覧ください。

外国人雇用時の注意点と支援体制
外国人材を受け入れる際には、適切な支援体制の整備が成功の鍵となります。
まず、在留資格の確認と適切な手続きが必須です。IT人材であれば「技術・人文知識・国際業務」、製造現場であれば「特定技能」など、業務内容に応じた資格取得が必要です。
次に、生活面でのサポート体制を整えましょう。住居の確保、銀行口座開設、役所手続きなど、日本での生活立ち上げを支援することで、早期の職場定着につながります。
また、社内の受け入れ環境整備も重要です。作業マニュアルの多言語化、やさしい日本語でのコミュニケーション研修、メンター制度の導入などが効果的です。専門的な手続きや支援については、外国人材紹介の専門企業に相談することで、スムーズな受け入れが実現できます。
まとめ:DX推進は「人材確保」から始めよう
製造業DXが進まない最大の理由は、推進できる人材の不足です。システムやツールを導入しても、それを活用できる人材がいなければ成果は生まれません。本記事で紹介したように、外国人IT人材の活用や特定技能外国人による製造現場の人手確保など、多様な人材戦略がDX推進の突破口となります。
株式会社ジンザイベースでは、製造業における外国人材の紹介支援を行っており、DX推進に必要なIT人材から、現場で活躍する特定技能外国人まで、幅広くサポートしています。人材確保とDX推進でお悩みの企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。


















